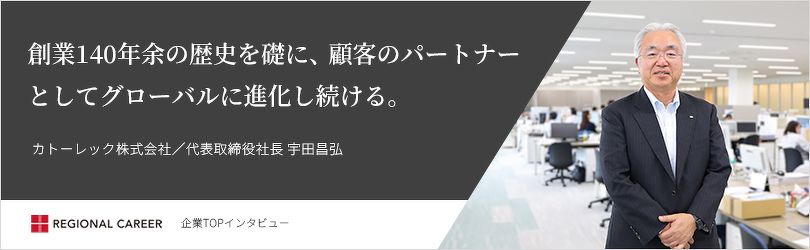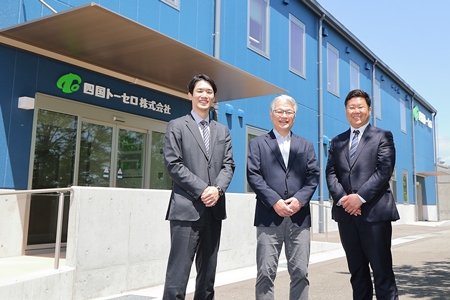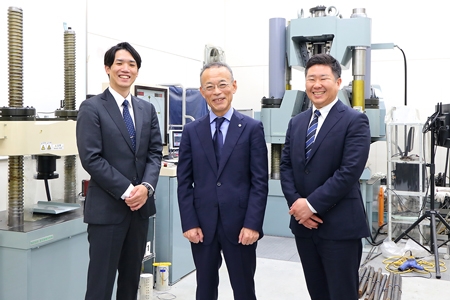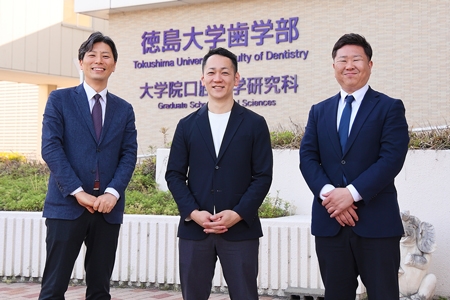グローバルな舞台で培った経験と、地元四国での新たな挑戦。
- 武市
- まずは、宇田社長のプロフィールからお聞きしてもよろしいでしょうか。
- 宇田
- 高知県の出身で、関西大学社会学部を卒業後、東京に本社のある証券会社に入社しました。もともと海外志向が強く、社内の留学試験を受けたりしたのですが、なかなか機会に恵まれず、そうこうしているうちにバブル崩壊の兆しが見えはじめ、証券会社で海外経験を積むことは難しい状況になってしまいました。そんな時に、求人広告で松下寿電子工業(現:PHCホールディングス)の募集を見つけたのです。当時、松下寿電子工業の海外輸出比率は8割と高かったので、「ここでなら海外での仕事ができるかもしれない」と、転職を決意しました。
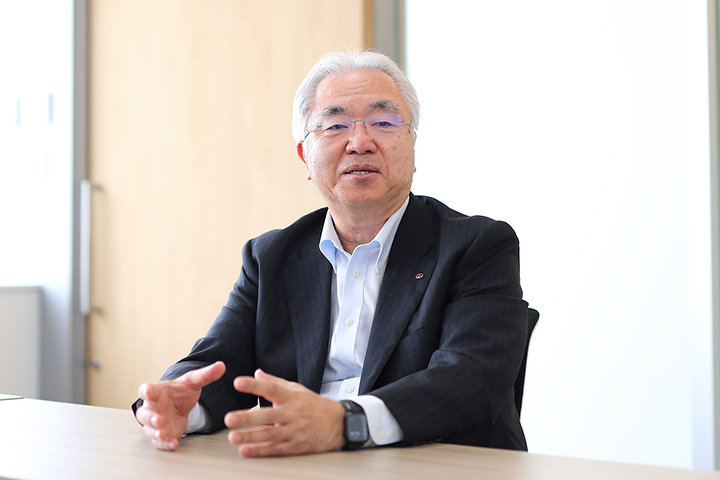
- 武市
- 松下寿電子工業ではどのようなお仕事をされていたのですか。
- 宇田
- 海外営業に従事できると思って入社したのですが、蓋を開けてみると、最初に任されたのは社長秘書の仕事でした。入社早々「君には社長の補佐をやってもらう」と言われて驚きましたね(笑)。本当の秘書の方は別にいらっしゃったので、私はいわゆる付き人のような役割です。英語ができたこと、それから社長が高齢でしたので、「いざとなったら若い君が社長を背負ってでも支えるんだ」と期待されての配属でした。
- 佐々木
- いきなり社長の側近業務とは、予想外のスタートですね。
- 宇田
- そうですね。ただ、常に社長と行動を共にする中で、海外出張へも随行させていただくなど、貴重な経験を積むことができました。秘書業務に数年従事した後、今度は上司から「海外への赴任を希望していたな」と声をかけられ、念願が叶いシンガポールに赴任することができました。シンガポールには5年ほど駐在し、電子部品の国際購買業務に携わりました。赴任当初は現地スタッフと私という2人の小さなチームでしたが、ちょうど円高が進んだ時期で、海外での部品調達が拡大し、最終的には20人ほどのチームに成長しました。直属の上司は日本にいたので、現地での基本的な判断は私に任されており、それが大きな学びと成長に繋がったと思っています。単に与えられた業務をこなすのではなく、自ら考え、主体的に事業を拡大していく面白さを知った時期でした。
- 佐々木
- 若くして大きな裁量を与えられたわけですね。
- 宇田
- はい。本当に貴重な経験でしたね。一度日本に帰任した後にアメリカのシリコンバレーに6年間赴任して、現地企業との事業提携や技術開発の窓口業務を担当したり、帰国後はCFOとして、スイスに本社を置く企業を買収し、世界35カ国で同時に事業を立ち上げるといったグローバルなM&Aも経験しました。こうした職務経験を通じて、事業全体を俯瞰し、国境を越えて多岐にわたる機能を理解・統合する能力が磨かれたと感じています。
- 武市
- まさにグローバルな舞台で、経営の中枢を担うご経験を積まれてきたのですね。そして2019年、カトーレックに入社されるわけですが、どのような経緯だったのでしょうか。
- 宇田
- 当時の加藤社長、現在の会長よりお声掛けをいただいたことがきっかけです。たまたま前職で事業の方向性に対する考え方の違いが表面化していたこともあり、思い切ってカトーレックへの入社を決意しました。自分としても、まさか四国に戻ってくるとは思っていませんでしたが、不思議な巡り合わせでしたね。しかし、以前からカトーレックのことは名前も事業内容も知っていましたし、海外展開に積極的だと聞いて興味を持っていました。カトーレックにはEMSと物流という二つの安定した事業基盤があり、良い顧客にも恵まれている。そこに私の経験を掛け合わせれば、さらに発展させられる余地があると感じ、チャレンジしようと決めました。
原動力は好奇心と挑戦意欲。人を繋ぎチームで未来を創る。
- 佐々木
- 宇田社長のキャリアをお聞きすると、常に変化を恐れず、新しいことに挑戦されてきた印象を受けます。
- 宇田
- 自分で言うのも何ですが、好奇心が人一倍強く、それが挑戦の原動力になっているように思います。証券会社からメーカーの松下寿電子工業に転職したこともそうですが、面白そうだと思ったらすぐに「やってみよう」と行動に移してきました。シンガポールでのチームの成長も、グローバルなM&Aの成功も、与えられたミッションだけを遂行するのではなく、自分の関心を広げて主体的に動いたことが成果に結びついたと考えています。
また、私の性格として、あまり悲観的に考えすぎず楽天的に構えるところがあり、それも行動力の源になっているように思います。困難な状況に直面した時も、もう一人の自分が頭の中にいて「おいおい大変そうだな、でも頑張れよ」なんて客観的にツッコミを入れている感覚があります。そうやって俯瞰して自分を見ることで気持ちを切り替え、踏ん張ってきたのかも知れません。どんな状況でもボールを落とさず愚直にやり抜く、そうした姿勢はぶらさずに貫いてきました。 - 武市
- 宇田社長はこれまで様々な組織を経験されてきましたが、カトーレックの組織風土に対してはどのような印象をお持ちですか。

- 宇田
- カトーレックに入社して最も新鮮だったのは、意思決定スピードの速さです。一般的に大手企業は承認プロセスが何段階もあり、手続きに時間がかかる傾向にありますが、カトーレックのようなオーナー企業は物事を判断して動き出すまでが非常に早いのです。加藤会長はオーナー経営者ではありますが、決してワンマンで独断専行というわけではなく、マネジメントチームの意見をよく聞いてくれます。その上で「やる」と決めたら実行が速い。私もその環境で、スピード感を大事にしつつ周囲と調和しながら経営判断を行うよう心がけています。幸い現場からのボトムアップの提案も上がってきますし、良い提案はどんどん採り入れていこうと考えています。
- 佐々木
- スピーディーだけれど独りよがりにならない。チームでの意思決定を重んじているのですね。
- 宇田
- チームワークはとても大切にしています。社員には、「チームプレイがちゃんとできる人」、そして「お客さまとのコミュニケーションがしっかり取れる人」であってほしいと願っています 。お客さまの要望が多様化・高度化する中で、社内の様々な部門とスムーズに連携する力を養うことはもちろん、お客さまの本当のニーズを的確に理解する能力をしっかりと鍛えていく必要があります。「伝える力」も重要ですが、その前提として「聞く力」、そして「理解する力」が求められます 。
「お客さまから学べる人は伸びますよ」と常々言っているのですが、お客さまの困り事や根本的なニーズを深く理解し、我々が持つソリューションと丁寧にすり合わせていく。このプロセスこそが、新たな価値の創造に繋がります 。カトーレックには、もともとチームワークを重んじる風土が根付いています 。こうした風土は、社内だけでなく、お客さまとの間にも強固なパートナーシップを築き、単なる取引を超えた関係性を構築します。そうした繋がりは、予期せぬ変化や困難に直面した際に組織の耐久力や適応力を高めてくれます。お客さまが一度カトーレックに発注いただくと、その後も継続してご依頼いただけるようになるという事実は 、まさにチームワークを大切にしてきた社風の賜物であり、模倣困難な競争優位性となっているのです。 - 佐々木
- チームワークという点では、今年の4月に竣工した高松本社工場においても、こだわられた部分が多いのではないでしょうか。
- 宇田
- おっしゃる通り、新たな高松本社工場の建設にあたってはコミュニケーションの改善も大きなテーマの一つでした。特に大切にしたのはワンフロアオフィスです。気軽に打ち合わせができるスペースを多く設けるなど、部門間の物理的な垣根を取り払うことで、何か課題が生じた際にも関係部署とすぐに直接話ができる。この近さは社員のコミュニケーション活性化につながっています。瀬戸内海を望めるよう設計された食堂も、そうしたコミュニケーションの場として活用できるようになっており、交流の促進につながればと考えています。
「ロジトロニクス」で進化するEMS事業。
- 佐々木
- カトーレックは歴史のある物流事業で認知している方が多いかと思いますが、EMS事業はどのように立ち上がっていったのでしょうか。
- 宇田
- きっかけは、お客さまから「部品の運送だけでなく、組み立ても手伝ってくれないか」という依頼を受けたことです。お客さまの要望に応える形で製造請負を始めたことが当社のEMS事業の始まりとなります。当初は特定顧客から下請け作業を請け負う形でしたが徐々に規模を拡大し、現在では9か国に12工場を持ち顧客の業界も幅広く展開しています。EMSは「電子機器の製造プロセスを受託するサービス」です。製造業のアウトソーシング先とも言えますね。海外ではEMSは当たり前のビジネスモデルとして確立されており、例えばAppleなどは早くから自社工場を持たず、外部のEMS企業に製造を委ねています。一方、日本のメーカーは伝統的に「自社工場で自社の製品を作る」スタイルが一般的でした。
しかし近年、日本でも変化が起き始めています。国内メーカーも独自の技術や固有の製造プロセス以外は外部企業を活用する動きが広まり、それに伴ってEMSの市場は年々拡大しています。 - 佐々木
- そうした市場において、カトーレックの強みはどのような点にあるとお考えでしょうか。
- 宇田
- やはり、祖業として培ってきた物流のノウハウを活かせることが大きな強みとなっています。カトーレックはEMSと物流の両事業でバランスを取りながら経営を行っており、我々はこの二つの事業を融合させた「ロジトロニクス」というコンセプトを掲げています。これは、「モノをつくる」エレクトロニクス事業と、「モノをはこぶ」ロジスティクス事業のシナジー効果によって、お客さまに新たな価値と高品質なサービスを提供し、強固な経営基盤を築いていく、という考え方です 。具体的には、製品の設計・製造から、配送、調達まで、サプライチェーン全体を幅広くサポートできる体制を整えていきたいと考えています。このロジトロニクスというビジネスモデルは、お客さまにとっては、製品開発から市場投入までのプロセスを一貫して任せられるという点で、複雑性の低減、効率性の向上、そしてサプライチェーン全体のコントロール強化といったメリットを提供できると考えています。特に近年のようにサプライチェーンの変動性が高まり、事業継続計画の重要性が叫ばれる時代において、設計から製造、物流までを包括的に提供できる当社の価値は、さらに高まっていくはずです。
- 武市
- 顧客ニーズについては、どのような変化を感じていらっしゃいますか。
- 宇田
- 昨今、EMSに対するお客さまの期待は一段と高まっています。昔は顧客の要求に従って製造することのみが求められていましたが、時代とともに求められる役割も広がっています。例えば、お客さまが指定した部品をこちらで手配するのは当然として、「もっと安価な代替部品を提案してくれないか」といったコストダウンの提案を期待されることもあります。また基本設計はお客さま自身が行う場合でも、「製品化に向けて一部設計を手伝ってほしい」「量産工程の設計や生産設備の準備に知見を貸してほしい」といったご要望も増えてきました。要するに、単なる下請け製造から一歩進み、開発・設計や部品調達など、ものづくりをトータルに支援する役割が求められるケースが増えてきているのです。
- 佐々木
- 以前に比べて提供する付加価値の範囲が広がっているというわけですね。

- 宇田
- そうです。ですから当社も、「できること」をどんどん増やしていかなければなりません。当社には基板実装をはじめとする電子部品組立の高度な技術とノウハウが蓄えられており、品質管理や生産管理の仕組みもしっかりしています。そうした現場力をベースに、今後は設計面のサポート力や部品調達の提案力といった領域を上乗せしていきたいと考えています。理想を言えば、お客さま視点で「自社がやりたいことをすべてカトーレックに任せられた」と思っていただけるようになるのが目標です。一朝一夕にはいきませんが、着実にステップアップしていきたいですね。さらに、当社は日本国内だけでなく海外にも製造拠点や取引先があります。インドや中国、東南アジアやメキシコにも展開していますので、そうしたグローバルネットワークも強みとして活かしながら、国内外でEMS事業を伸ばしていきたいと考えています。
地域社会への貢献と、四国で働く魅力。
- 武市
- 物流事業については、2026年9月に番の州臨海工業団地に新たな物流施設を建設予定とお聞きしました。この物流施設建設には、どのような狙いがあるのでしょうか。
- 宇田
- 四国は人口減少という大きな課題に直面していますが、物流の側面においてもドライバー不足、輸送能力の低下、物流コストの高騰といった深刻な問題が生じることが想定されています。そうした状況下において当社は、「四国の物流は我々が守る」という強い使命感を持って事業に臨んでおり、その具体策として四国の玄関口である番の州に大規模な物流施設を建設し、本州と四国を結ぶ物流の結節点としていくことを計画しています。今年に竣工した高松本社工場でも100名の新規雇用を予定していますが、物流施設においても新たに80~90人の方を雇用し、四国の物流の活性化に繋げていきたいと考えています。
また、物流業界全体の人手不足の解消には「定着」こそが重要だと考えていますので、単に雇用するだけでなく、作業環境の改善や管理職の意識改革といった取り組みも推進しています。四国における物流課題への対応は、単に目先の利益を追うのではなく、地域貢献の役目も果たす長期的視点に立った投資であり、これはカトーレック全体の安定した事業基盤の形成にも繋がると考えています。 - 佐々木
- まさに四国の未来を支える取り組みですね。地域貢献という点では、高松市にある「四国村」の運営も大きな柱になっているのではないでしょうか。
- 宇田
- そうですね。四国村は四国各地から築100年以上の古民家や旧跡を移築し、伝統的な暮らしと文化を現代に伝える野外博物館です。これは創業者が社会的使命と考えて始めた事業で、現会長の加藤が建物を残すだけでなく「その古民家で営まれていた暮らしごと残そう」という発想で、古民家にまつわる様々な資料映像を作成・公開しています。こうした活動は、時間の経過とともに一層価値が高まっていく取り組みだと思っています。古民家そのものは老朽化との戦いですが、今から同じものを集めようと思っても、もう手に入らない貴重な文化財ですから、未来に伝えていく意義は大きい。今後も末長く守り続けていきたいですね。

- 武市
- 最後に、四国で働く魅力について宇田社長の考えをお聞かせください。
- 宇田
- 私自身、生まれ育った四国を離れて東京や海外で長く働いてきましたが、地元に戻ってきて感じるのは生活環境の良さです。特に香川はコンパクトにまとまっていて生活の利便性が高く、通勤ひとつとっても快適ですよ。それに若い世代の方にとっては住宅の面でも将来設計が立てやすいのではないでしょうか。都会だと家を買うとなるとハードルが高いですが、香川なら現実的にマイホームを持つことも視野に入ります。生活面でのゆとりがある分、仕事にも集中できますし、家族との時間も取りやすい。働きやすく暮らしやすい環境が整っていると思います。
また、「地方に行くとキャリアの幅が狭まるのでは」と心配される方もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。少なくとも当社の場合、拠点は香川にあってもビジネスの範囲は日本全国・世界各国に広がっています。取引先も海外に複数ありますし、プロジェクトによっては海外出張や駐在のチャンスもある。四国にいながらにして世界を相手に仕事ができるのです。

- 佐々木
- 地方にいながらグローバルに活躍できる。とても魅力的なメッセージですね。
- 宇田
- 社員には「積極的に外の世界を見てきなさい」と伝えていますが、たとえ暮らしのベースが四国でも、視野は全国・世界に向けて開かれているべきです。当社には地域に腰を据えて働きつつ、海外研修や大型のプロジェクトに挑戦できる機会が多くあります。四国で暮らしながら、大きな舞台で成長できる。そんな可能性がここにはあります。
- 武市
- 四国だからこそ得られるキャリアがある、というわけですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。
当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、カトーレック(株)代表取締役社長 宇田昌弘氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

宇田 昌弘
カトーレック(株)代表取締役社長
高知県出身。関西大学社会学部を卒業後、証券会社を経て、1991年に松下寿電子工業(現PHCホールディングス)に入社。海外赴任を通じた電子部品購買や事業提携、製薬会社の事業買収プロジェクトリーダー、さらにはCFOといった要職を歴任し、グローバルな視点と財務戦略における高度な専門性を培う。2019年、カトーレック(株)に常務執行役員経営企画担当として入社し、2023年4月に取締役専務執行役員としてEMS事業本部の本部長に就任。2025年4月、同社代表取締役社長に就任。

佐々木 一弥
(株)リージェント 代表取締役社長
香川県さぬき市出身。大学卒業後、2007年に株式会社リクルートに入社。求人広告の企画営業職として、香川・愛媛にて、四国に根差した企業の採用活動の支援を中心に、新拠点や新サービスの立ち上げも経験。2010年に販促リサーチを行うベンチャー企業の創業メンバーとして参画。創業の苦労と挫折を経験。2012年、株式会社リージェントの創業メンバーとして入社。2019年より代表取締役社長に就任。子どもと焚き火をするのが至福の時間とのこと。

武市 理佐
(株)リージェント コンサルタント
高知県高知市出身。新卒で東京の求人広告会社(リクルートトップパートナー)に入社し、東京都港区を中心に、メーカー・不動産・IT・広告など多岐にわたる業界の大手上場企業からベンチャー企業までを対象に、新卒および中途採用の支援に従事。2017年、「地元・高知のための仕事がしたい」という思いからUターン。大学法人および県庁にて、地域連携や産学官民連携事業に携わる。学生の就職支援や経営者を対象としたビジネスセミナーの企画・運営を通じて、高知で働く魅力創出に尽力。リージェント入社後は、四国全体の地域活性化を目指し、四国へのU・Iターンを希望する求職者に対してキャリア相談や転職支援を行い、四国とのご縁を結んでいる。