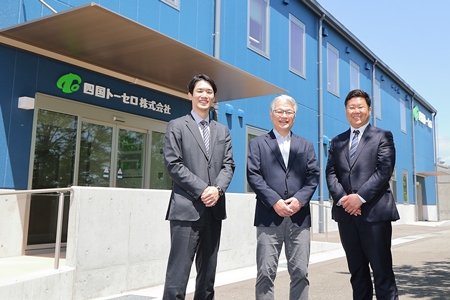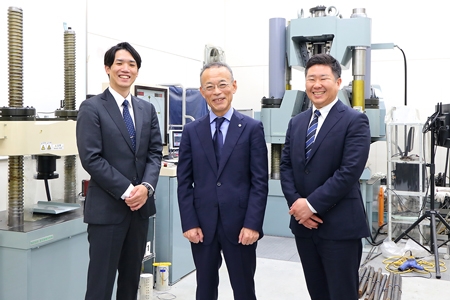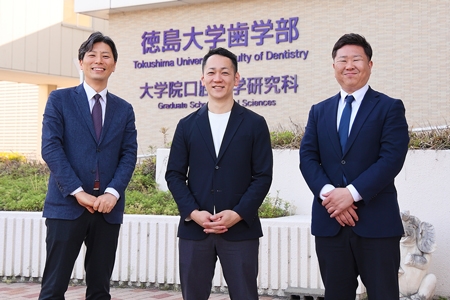人間味のある職場で、品質保証部門をゼロから築くやりがい。
- 溝渕
- 丸野さんはご自身も奥様も香川ご出身だそうですね。地元へのUターン転職を考えられたきっかけは何だったのですか。
- 丸野
- 地元で暮らす高齢の親の面倒をみたい、というのが一番の理由です。高専を卒業後、関西の企業に就職。長く関西で暮らしましたが、もともと住む所にそれほどこだわりがあったわけではないのです。子どもは既に独立していて、夫婦でUターンするのに障害もありません。今まで学んできたスキルを発揮できる会社なら、どこでもいいと思っていました。
前職には、品質保証部の部長職に就いていたこともあって、かなり引き止められました。でも課長や係長が育っており、私が抜けても部門に迷惑をかける心配はなかったため、迷いませんでした。

- 四ノ宮
- 四国化成ホールディングス(株)には、化成品事業を展開する四国化成工業(株)と建材事業を展開する四国化成建材(株)という2つの主要な事業会社があります。丸野さんの転職先は四国化成建材で、前職とは事業領域が違いましたが、不安は感じませんでしたか。
- 丸野
- 前職で扱っていたのは半導体製造装置で、四国化成建材はフェンス、カーポートなどのエクステリア製品や、内外装材・断熱材といった建材がメインですから、うまくアジャストできるか、という不安がなかったわけではありません。しかし、全く知らない分野に入るのは、新たな知識を習得するチャンスでもあります。前職が法人相手のBtoB製品だったので、建材のようなBtoC分野で仕事して、お客さまの喜ぶ顔に触れてみたいという期待感もありました。
- 溝渕
- 丸野さんが入社した時、四国化成建材の品質保証部門はどのような状況だったのですか。
- 丸野
- 四国化成建材には品証部門がまだなかったんです。そこで部門の立ち上げからお願いしたい、ということでした。品証の基本的な考え方は、業界が変わっても共通する部分が多いのです。前職でもそういった品証の体制づくりから関わった経験もありますし、自分のスキルを利用して新しい組織を作り上げることで、私の価値を発揮できるのではないか、と思いました。
- 四ノ宮
- 従業員数2,000人以上の大手企業から200人の四国化成建材への転職ですが、違いやギャップを感じましたか。
- 丸野
- 最初に思ったのは「人間味のある会社だ」ということですね。困ったことがあると、自分の担当範囲でなくても積極的に助け合おう、とする雰囲気があります。人間的に「いい人」が多いのだと思いますね。品証の活動に対して現場が協力的でない会社も珍しくはなく、「そこは自分の担当範囲じゃない」といって知らん顔をされると、課題の把握や解決策の構築に時間がかかってしまいます。しかし四国化成では、まだそういう苦労を味わっていません。損得ではなく、全員で協力して問題を解決する姿勢が根付いている。これは貴重なことだと思います。
ただ、人が良すぎるせいか「相手が嫌に思うだろうな」という意見を避ける傾向にあるかもしれません。これは美徳とも言えますが、遠慮が過ぎるのもよくありません。現場の課題を拾い上げる役割を担う品証が言うべきことを言わずにいると、存在意義がなくなってしまいます。その点は注意したいですね。
現場を確認し、課題を俯瞰し、部門を巻き込んで問題を解決する。
- 溝渕
- 丸野さんが品質保証において重視されているのは、どういった点でしょうか。
- 丸野
- 一般に「品質管理」と「品質保証」という職種は名前が似ているので混同しがちですが、役割は明確に異なります。「品質管理」の役割は、製品の質を担保することです。仕様に適合した製品になっているか検査したり、そういった製品を作るように製造体制を整えるのが主な業務です。これに対し「品質保証」は、もう少し広い視点で、事業や製造の仕組み全体を見渡し、課題を捉えて解決することが主な役割になります。
課題解決が役目なので、「あれをやれ、これをしろ」と上から目線で各部門に言いたいことを言う品証部門も、世の中にはたくさんあります。でも私は、そういうやり方は正しくないと考えています。課題は関係者が一丸となって解決するものですので、関係する現場・部門を巻き込んで一緒にやることが大切だと考えています。それが品証の面白さだとも思うのです。 - 溝渕
- 現場に行くことも多いのですか。
- 丸野
- 現場での事実確認が、品証の業務のスタートです。建材の場合、工務店やゼネコンが当社の製品を購入され、施工現場で使用されます。もしそこで不具合が発生した場合、施工の現場に行ってみなければ問題の発生状況はわかりません。なので、できる限り現場に足を運ぶようにしています。
そこで事実が確認できたら、次は少し俯瞰して原因を追求します。製造段階にミスがあるのか、工程の連携やプロセスの問題か。ミクロとマクロの両方の目線で原因の根本を見定めます。その上で、関連する部門を巻き込んで解決を図るわけです。 - 四ノ宮
- 四国化成建材の品証に取り組んで約1年ですが、手応えはいかがでしょう。

- 丸野
- 四国化成は「Challenge 1000」という長期ビジョンを策定し、2029年までにグループ売上1,000億円を達成しようと、事業会社が努力を重ねています。会社が変わろうとする時、課題が発生することはむしろ当たり前です。
この1年やってみて、いろいろ課題を抽出できました。今は課題のプライオリティーを考慮し、対応を進めています。並行して、ファクトを見て課題を抽出する、という手法を身に着けてもらうため、メンバーに向けたロジカルシンキング教育も開始するところです。
Challenge 1000で示された変革方針の中に「価値づくり」があります。「価値づくり」とはつまり、カスタマーに対してどれだけいい商品とサービスを提供できるか、ということです。そのためには、商品やサービスを生み出すプロセスが適正でないといけません。そこに品証の存在意義があります。 - 溝渕
- 2025年からは四国化成ホールディングスの品質保証部長も兼務することになった、とお聞きしています。
- 丸野
- 既に述べた通り、業界が変わっても、品証の基本は同じです。売上アップを目指して増産したり新商品を作ったり、そのために人を増やしたりして従来のプロセスを変えると、必ず問題が発生します。四国化成グループ全体で成長しようと考えるなら、品証の手法を、あらゆる事業領域で横串を刺すように定着させる必要があるのです。
今年から早速、いろんな領域の部門に足を運んでいます。化学の分野は前職と近いので、それほど違和感はありません。これに加えて、四国化成グループ各事業会社の経理、財務、人事、法務、税務などを統括する四国化成コーポレートサービス(株)や、ホールディングス自体の管理部門でも品証を実践しています。管理部門はものづくりの現場ではありませんが、やることは変わりません。ファクトを現場で確認し、原因を抽出し、関連する部門を巻き込んで解決を図っていきます。 - 溝渕
- すごいスピードで担当範囲が広がっているように思いますが、大変さはありませんか。
- 丸野
- 担当範囲が広がることは別に問題ありません。一番大変なのは、各現場で正直に話してもらえない、といった事態になった場合です。現場の情報が収集できないと、適切な解決策につながりません。ですので、とにかく私には何でも言ってください、と伝えるようにしています。「丸野なら包み隠さず話しても大丈夫だな」と相手に思ってもらえるようにしないといけません。
その点でも、人間関係の良好な会社というのはいいですね。こちらが真摯に向き合えば、みんな正直に本音を語ってくれますし、困ったらみんなで何とかしようと努力してくれる。品証としてやりがいがありますよ。
品証の経験は不要。重視しているのは、モノづくり業界での“課題認識力”と“課題解決力”。
- 四ノ宮
- 四国化成ホールディングスの品質保証部を、中長期的にどういう組織にしていきたい、とお考えですか。
- 丸野
- みんなの困りごとを解決する組織でありたいと思います。どのような領域の問題であれ、品証に言えば何とかしてくれる、と頼もしく思ってくれるような。様々なプロセスに横たわる課題を解決すれば、社員は意欲を持って仕事できます。その意欲は、いい商品やサービスに結びつくはずです。
- 溝渕
- 今、品証のメンバーは何名いらっしゃるのですか。
- 丸野
- 四国化成建材の品証は3名。四国化成ホールディングスの品証も、同じく3名です。今は課題に優先順位をつけている段階なのでこの人員で十分ですが、「この課題を1年以内で解決しないと、売上1,000億円達成の弊害になる」など実践段階になったら、もっと人手が必要になるかもしれません。会社からも「良い人材がいればいくらでも連れてきてほしい」とも言われています。ただ、中途採用マーケットに品証系の経験者はそれほど多くないでしょうね。品証の数自体が少ないので。
- 溝渕
- 品証で働く人材を採用したいとなった時、期待する経験や技術などはありますか。

- 丸野
- ものづくり業界で働いた経験があるといいと思います。特に重視したいのは、課題認識力ですね。「このやり方は正しいのか」という思考ができるかどうか。品証にとって、課題を認識して設定する力はとても大事です。例えば、商品に傷が入っている、という問題に直面した場合、傷をなくすためにどうするか。商品を全数検査する方法もありますね。どの段階で傷がつくのかを確かめ、傷のつかない作業法を構築しても良いかもしれません。課題を俯瞰して見なければ、適切な解決策はつかめません。
それから、品証の経験はなくても構いません。設計業務の経験者とか、生産技術の経験者でもいい。前職の品証部門には、機械が得意な人、電気に強い人など、いろんなバックボーンを持つ人が混在していました。
また、他部門とやり取りすることが多いので、コミュニケーションを苦にしない人が向いています。現場にいる人たちざっくばらんに話のできる関係性を保つことが、問題の的確な把握と解決につながります。 - 四ノ宮
- 課題設定力、解決力があればOKなら、いろんな経験の持ち主が活躍できそうですね。
- 丸野
- 最初はわからないこともあると思いますが、自分で考えてみて答えが出なければ気軽に頼ってもらえばいい。
私だって、自分で考えて答えが見つからない場合、上司や社長に聞いたりします。自分一人で何とかしないと…とプレッシャーを抱えていないので、ストレスなくやれているのです。その意味でも、気軽に話ができる四国化成の職場環境には魅力を感じますね。業務がうまく行っている時は、やることにそれほど差はありません。しかし、問題が発生した時に素早く協力体制を構築できるかどうかは社風が大きく関わってきます。
私は、香川県の周辺の企業で品質部門を担当する人と交流する機会もありますし、時には他社に出向いてセミナーを実施することもあるのですが、どこに行っても真面目で人の良さを感じます。これは香川の県民性、四国の地域性なのかもしれませんね。 - 溝渕
- 今後は海外でご活躍、といった可能性もあるのですか。
- 丸野
- 四国化成建材も海外進出を検討しているので、十分あり得ます。まずは既にアジアやアメリカの市場に進出している住宅メーカーと連携していく形になると思います。私としては、いつでもOKです。前職でも海外の顧客に「すぐに来てくれ」と呼ばれて飛んで行くことがよくありました。
これからは、海外ビジネスに関わりたいという方も、四国化成ホールディングスにとっては貴重な人材になるのではと思っています。
貢献感が得られる環境で、地元の未来に寄与できる喜び。
- 溝渕
- 四国ならではの働く価値について、丸野さんはどうお考えでしょうか。
- 丸野
- 大都市は人口も多いし、マーケットが大きい。ビジネスのチャンスが大都市に多いのは確かです。一方、地方には、ゆったりした暮らしがある。自然に恵まれているし、人が優しい。後は自分に合った仕事さえ見つかれば、充実した人生が送れるように感じます。規模では東京や大阪に劣るものの、独自の創造性を持ち、社風も良い四国化成のような会社がローカルにはあります。そういう会社で活躍することで、地元の発展に貢献したいという人はいるはずです。
私も同じです。年齢的に組織で力を発揮できるのはあと10年くらいかもしれませんが、その期間で品証部門を確立し、後進を育て、以降30年くらいは何の心配もいらない体制を構築しよう、という思いで香川に戻ってきました。香川で長く歴史を刻んできた会社の未来に寄与することが、私にとっての地域貢献です。

- 四ノ宮
- 大都市圏で大きな仕事を任されていた人の中には、「地元に戻ったら仕事がスケールダウンするのでは」と感じられる方もおられるようです。
- 丸野
- 企業規模が小さくなるかもしれませんが、担当する仕事の範囲は、逆に大きくなると思います。大手企業の中の限られた一部分を担当するか、地方の中小企業で幅広い範囲を担当するか。どちらにやりがいを見出すかは人によって異なりますが、私は後者に魅力を覚えます。
もちろん、あくまで年収にこだわるなら大手にとどまった方がいい。でも地方ではそれほど生活資金がかからないし、税金なども含めて考えると、可処分所得が激減した感じはなかったです。
大手の工場では組織が大き過ぎて、各部門が協力的でなかったり、縦割りになっていてお客さまの方を向いていない、といったことが起こりがちです。そんな状況だと、自分が何の役割を果たしているのかわからず、歯車の一つのように思えてしまうこともあるのではないでしょうか。
四国化成にそういう空気はありません。経営者との距離も近いので、何かあればすぐ相談もできますし、あまり細かいことに口を出されたりもしません。自然に恵まれた暮らしと、みんなで協力して同じゴールを目指せる仕事が、ここにはあります。大都市圏で好きでもない仕事を続けながら窮屈に暮らすのとは、180度価値観の違う人生が送れますよ。
<関連コラム>

丸野 大輔
四国化成ホールディングス(株)品質保証部 部長
1971年生まれ。香川県出身。高等専門学校卒業後、京都本社の(株)SCREENセミコンダクターソリューションズに入社。製造技術や海外現地法人の技術責任者を経て、同社の品質保証部の部長として部門戦略の立案やメンバーマネジメントに従事。50歳を過ぎた頃から、高齢の親が地元で暮らしていることを考え、Uターン転職を志向し始める。2023年10月、四国化成建材(株)に入社し、品質保証室の立ち上げを担当。2024年1月、同室の室長に就任。さらに2025年1月からは、四国化成ホールディングス(株)の品質保証部部長に就任し、四国化成グループ全体の品証部門を統括している。

溝渕 愛子
(株)リージェント チーフコンサルタント
高知県高知市出身。大学卒業後、総合リース会社に就職。地元の高知支店に配属されリース営業に従事。その後、大阪に転居し、株式会社リクルートに入社。HRカンパニー関西営業部の新卒・キャリア採用領域で企業の採用活動をサポート。また、派遣領域では関西・中四国エリアの派遣会社への渉外業務に従事。四国へのUターンを決意してリクルートを退職。香川県の人材サービス企業に転職し、管理部門にて、社員の労務管理、新卒採用活動に従事。その後、株式会社リージェントに入社。今ハマっているのは、限られた自由な時間を有意義に過ごすこと。1日にジャンルの異なる数冊の本を、少しずつ読むことを楽しんでいる。

四ノ宮 こころ
(株)リージェント チーフコンサルタント
香川県出身。大学卒業後、ITベンダーを経て株式会社リクルートへ入社。新卒採用における組織課題抽出、採用計画策定、企業広報及び選考プロセス設計から入社後育成までのコンサルティングに携わる。10年間のキャリアを経て関西への転居を機に、キャリアコンサルタントとして自身の専門性を高めたいと考え、地元四国の貢献に繋がれば、との想いから株式会社リージェントへ入社。現在は同社大阪オフィスにて勤務。