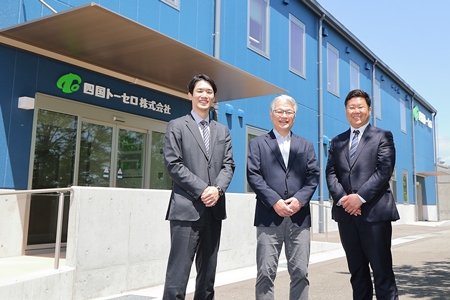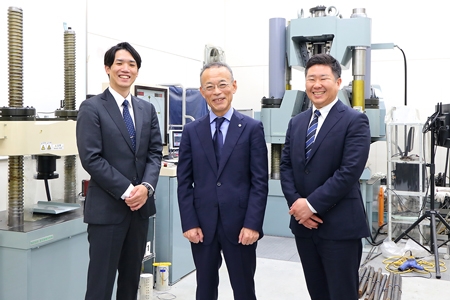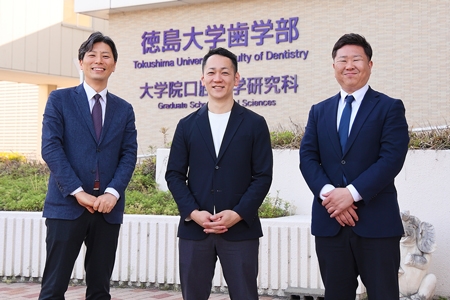社長の熱意と小豆島の魅力に、心を動かされた
- 武市
- 最初にみなさんのプロフィールをお聞かせください。
- 島本
- 私は2010年の中途入社です。催事や店舗、コールセンターなど、通販以外の営業領域の責任者を担っています。出身は小豆島で、大学進学のため大阪に出ました。そのまま大阪で就職し、OA機器や産業機器メーカーで営業としてキャリアを重ねました。都会での生活に不満があったわけではないのですが、歳を重ねるうちに島を魅力的に感じることが増えてきまして。食は美味しく、生活環境も整っていて不自由がなく、心の底から落ち着ける場所。帰省の度にそう感じ、自然と島へ戻ることを考えるようになっていました。
具体的に転職先を探す中で出会ったのが、井上誠耕園です。当時は会社のことを全く知らず、「とりあえず受けてみよう」と、あまり構えずに面接に臨みました。ところが実際に面接に行くと、社長の放つオーラに圧倒されました(笑)。「小豆島から日本を元気にする!」という熱量と共に、販路拡大をしていくためのビジョンを熱弁されました。こんな会社が小豆島にあったのかという驚きとともに、この会社で経験を活かしたいと思い、入社を決めました。

- 武市
- 島を出たことで気が付いた小豆島の魅力とは、具体的にどのようなものだったのですか。
- 島本
- 漁師の家で生まれ育ったので、我が家の食卓には毎日のように魚料理が並んでいました。イカの刺身や魚の煮付けなど、今思えばとても贅沢な食事だったのですが、中高生の頃はそういった食事が嫌いでした。部活でいつもお腹を空かせて帰っていたので、ガッツリした肉料理を食べたいと思うことが多かったのです(笑)。
やがて大学進学を機に一人暮らしを始め、自分の好きなものを自由に食べられる環境になりましたが、意外にもすぐに飽きてしまいました。そんな中、帰省して久しぶりに採れたての新鮮な魚を食べたとき、「なんて美味しいんだ」と感動したのを今でも覚えています。それがきっかけで魚が好きになり、同時に島の雰囲気の良さも改めて実感するようになりました。
ある意味、「食」が原点となってUターンを意識するようになり、「いつか小豆島に帰りたい」という思いが次第に大きくなっていきました。 - 武市
- 豊かな食によって、島の魅力を再認識されたのですね。斎藤さんはいかがですか。
- 斉藤
- 私は香川県三豊市の出身で、大学は徳島で過ごしました。その後、2014年に新卒で井上誠耕園に就職しました。大学のゼミでは、農村や里山を訪れてフィールドワークを行い、地域再生について考察する研究に取り組んでいました。山あいの地でトマトを栽培している農家の方や、地域を盛り上げようと奮闘している若いレンコン農家の方にお会いし、お話をうかがいました。農業の衰退が叫ばれる中で、皆さんがキラキラした目で「農業には可能性がある」と語る姿に、強い衝撃と感動を覚えました。そうした出会いを通じて、地域の自然や食、そして農業に関わる仕事がしたいという想いが強くなっていきました。
- 佐々木
- 井上誠耕園を就職先として選ばれた決め手はなんだったのでしょうか。
- 斉藤
- 何社か選考を進む中で、自分の研究テーマに最も近い事業を展開していたのが井上誠耕園でした。当時、井上誠耕園は新卒採用を始めてまだ4年くらいだったのですが、小規模ながらも採用活動にとても意欲的に取り組んでいました。面接で社長の話を聞く中で、「地域を元気にしたい」「農業を活性化したい」という熱意がしっかりと伝わってきたのです。そして、私が感じていた農業に関する課題意識にも真摯に耳を傾けてくれました。ここでなら、大学で学んだ地域再生の学びを実践し、抱えていた課題の答えを見出せるのではないかと感じました。
大学の同期が銀行や自治体などに就職する中で、「島に将来性はないのでは」と心配する声もありました。また、両親も私に地元へ戻ってきてほしいという思いを抱いていたと思います。しかし、島とはいえ同じ香川県内ですから、特別に遠方というわけではありません。最終的には、「自分の人生なのだから、悔いのない選択をしよう」と、井上誠耕園への入社を決意しました。 - 武市
- 下地さんはいかがですか。
- 下地
- 私は、生まれも育ちも小豆島です。実家は7代続いていた農家で、幼い頃から畑で育ったみかんを食べたり、裸足で畑を走り回ったりしながら育ちました。学生時代は野球に打ち込み、高校時代に出会ったコーチからの教えが、今の自分の土台を築いています。そのコーチに出会うまでは、島で暮らしているという環境の中で、知らず知らずのうちに自分自身で限界を決めてしまっているところがありました。しかし、「本気で取り組めば、どこにいてもトップは目指せる」と教えられ、実際に甲子園常連校との練習や試合を経験する中で、自分たちの力が通用することを肌で感じることができました。それ以来、高い目標を持ち、自ら限界を定めずに努力を続ける姿勢を大切にしています。
その後、関西の大学に進学し、当初は体育教員かスポーツトレーナーを目指していたのですが、次第に小豆島のことを思い出す機会が増えていきました。特に秋祭りの時期に帰省し、地元の太鼓の音を耳にすると、何とも言えない懐かしさを感じるのです。島に戻りたいという気持ちをどうしても拭いきれず、就職活動の終盤になって井上誠耕園に「まだ面接していただけますか」と直接連絡し、何とか採用していただきました。 - 佐々木
- 井上誠耕園のことは以前から知っていたのですか。
- 下地
- いえ、そこまで深くは知りませんでした。ただ、小豆島の企業を調べていた際、ホームページに掲載されていた社員の方々の表情や、社長の農業に対する熱い思いに触れ、直感的に「ここだ」と感じました。野球を引退して以来、心から没頭できるものに出会えていなかったのですが、「小豆島を本気で元気にする!」という社長の熱意に強く心を動かされ、ここでなら再び夢中になれると確信し、Uターンすることを決めました。

お客さまとのリアルな接点を持ち、ファンになってもらう
- 佐々木
- 島本さんは管理職として催事、ショップ、コールセンターを見ておられますが、どのようなテーマや課題感を持たれていますか。
- 島本
- 催事チームでは、デパートやイベント会場などに出店し、商品の特長や背景にあるストーリーを、お客さまに実際に商品を手に取っていただきながらお伝えすることを大切にしています。どれほど優れた商品であっても、お客さまにその価値を知っていただかなければ購入にはつながりません。そのため、単に商品を販売するのではなく、「どうすればファンになっていただけるか」を常に意識しながら接客することが重要だと考えています。
売上構成比では通信販売の割合が大きいものの、催事での接点を通じて当社を認知していただくケースも多く、相乗効果として通信販売にも良い影響をもたらしていると考えています。通信販売市場は年々競争が激化しており、オンライン上の接点だけでは限界が見えつつあります。今後は、リアルでの接点とオンラインをいかに効果的に組み合わせて活用していくかが、重要な課題になると感じています。そのため、催事や店舗での販売は、お客さまに直接想いを伝え、ご意見や反応をうかがうことができる貴重な接点として、今後ますます重要な役割を果たしていくと考えています。 - 佐々木
- 催事はどのくらいの頻度で実施しているのでしょうか。
- 島本
- 多い時は、一ヶ月で6ヶ所ほどのデパートを回ります。企画打ち合わせからスペース設営、販売まで、全て自社で手掛けており、他社に委託はしていません。これは「自分たちで作ったものを、自分たちで売る」という社長のこだわりを具現化したものです。仲間の作った商品だから自信を持って売れますし、実際にお客さまと対峙するからこそ、商品改善に役立つ声が聞けるわけです。
開催場所は、できる限り過去に出店実績のない地域を選ぶようにしています。デパートのお客さまは、長く継続的なお付き合いを大切にされる傾向があるため、都市部か地方かといった先入観にとらわれず、さまざまな地域に積極的に足を運び、新たなお客さまとの出会いを広げていきたいと考えています。 - 武市
- 現場で動く下地さんは、催事の価値や楽しさはどういったところにあるとお考えですか。
- 下地
- 催事販売ではお客さまにお声がけしながら、生活ぶりをお聞きしたり、健康や美容の悩みを尋ねたりしており、時には商品と関係ない雑談に花が咲いたりもします。何より楽しいのが、井上誠耕園の商品に対するお客さまの反応を、間近で見られることです。ご意見は通販でもお聞きできますが、嬉しそうだったり驚いたりするお客さまの表情は、催事や店舗でないとわかりません。
通信販売での購入理由として、「催事で購入してとても良かったから」とおっしゃってくださるお客さまも多く、やりがいを感じています。接客の際に「小豆島ではレストランとショップが一体になった店舗があるので是非来てくださいね」とご案内もします。実際に小豆島までお越しいただいたお客さまもいらっしゃいました。また、催事に行った翌年に同じ百貨店へ出店した際、前年に来られたお客さまから「待ってたよ」と声をかけていただくこともあります。
新規のお客さまだけでなく、既存のお客さまとの関係を継続し、ファンになっていただくためにも、私たち自身が島から出向き、直接お話しすることが重要だと感じています。 - 武市
- 斉藤さんはいかがでしょう。新卒で入社して、どのような業務に携わってこられたのですか。
- 斉藤
- 新人の多くは、まずコールセンターに配属され、お客さまとのやり取りを学びます。私もそこで経験を積んだ後、企画部門へ異動となりました。当時、会社として化粧品分野を強化していくという方針もあり、「化粧品開発を担当してほしい」とのミッションを託されました。最初は自分にできるかな、と不安に思っていたのですが、やればやるほど面白くなり、仕事にのめり込んでいきました。
その後は、通信販売会員にお届けするカタログの制作にも携わるようになり、現在は広報も兼務しています。テレビ・雑誌・新聞・Webなど各種メディアに向けて当社を取り上げていただけるよう働きかけ、社内外の調整を行うことが主な業務です。そのほかにも、お客さま向けのイベント企画をはじめとする、社外向けPR業務も担当しています。お客さまと向き合い、「今、何を求められているのか」を考え、それを形にしていく仕事は、すごく楽しいですね。

- 佐々木
- さまざまな魅力ややりがいを感じられているのですね。一方で、井上誠耕園が抱えている課題は何だと思いますか。
- 島本
- 当社は社員一人ひとりの成長意欲も高く、新しいことに積極的にチャレンジできる環境が整っていますが、その一方で、やりたいことを次々に実行に移していくと、人手が追いつかず、結果的に兼務が多くなってしまうという課題も発生します。一つの業務をより深く掘り下げて取り組みたい、突き詰めたいと思っても、現在の体制では難しい部分もあるのが実情です。こうした点は、会社が成長の途上にあるからこその課題と言えるかもしれません。
- 斉藤
- 社長は判断が非常に早く、方向転換なども迷いなくスピーディーに進められます。広報の立場としては、社長の課題意識を捉え、業務に反映していくことが求められますが、社長は私たち社員には見えていない領域まで視野に入れて経営判断をしているため、考えを汲み取るのは容易ではありません。
それでも、社長の思考に食らいつき、自分なりに咀嚼し、社内外に適切に伝えていくことで、少しずつ社長の視点の一端が見えてくることがあります。「農業で日本を元気にしたい」という軸は常に一貫しており、変わるのはあくまでゴールに向かうルートや進み方だけです。だからこそ、変化のスピードに柔軟かつ迅速に対応できるようになりたいと思っています。そこに、私自身の成長の機会もあると感じています。 - 下地
- 課題がいくつかある中で、一つずつ社長が掲げる高い目標を、諦めることなく着実に実現していきたいと考えています。キャリアの浅い頃は、日々の業務に追われ、仕事の意味や目的を深く考える余裕はありませんでした。しかし、少しずつ物事を俯瞰して見られるようになり、自分の担当業務がどのようにお客さまの喜びや農業の発展につながっているのか、その意図を理解できるようになってから、仕事に対する面白さややりがいが深まったと感じています。
私たち一人ひとりの成長が、そのまま会社の成長へと直結していく。その実感を持ちながら、やりがいと責任感を持って日々の業務に取り組んでいきたいと思っています。
私たち自身が原動力となり、事業を進化させる
- 佐々木
- みなさん自身が考える事業展開やビジョンについてもお聞かせください。
- 島本
- 社長はいつも「小豆島は日本の課題の縮図。ここで課題を解決できれば、日本全体の活性化に役立てられる。」と言っています。私もその理念に共感しているのですが、それを実現するためには、私たち一人ひとりが主体的に行動し、事業をどのように育てていくかを考えていかなければなりません。
たとえば、「らしく園」を基点とした事業展開に注力していくことも、有効なアプローチの一つです。2017年よりドレッシングやジャムの工場、レストラン、店舗の複合型施設として運営してきましたが、この拠点活用を更に加速させて、新たな小豆島の賑わいスポットに成長させていきたいと考えています。お客さまに農園や製品づくりの現場を見ていただき、小豆島の魅力を体感していただくことで、より深い繋がりを築いていけると思っています。 - 斉藤
- 私も同じく、一人でも多くのお客さまが訪れて、たくさんの喜びを感じてもらえる場所として、らしく園の展開を促進していきたいという気持ちがあります。広報・企画の視点でいうと、らしく園でファンミーティングを積極的に開催してみたいですね。従業員がお客さまの本音に触れる良い機会にもなるのはないかと、考えるだけでワクワクします。
社長は「農業からものづくり、販売までを一貫してつなげる6次化を発展させるためには、多様な人材が集まって多彩な才能を併せ持つことが必要」とよく言っています。その言葉の通り、私たち一人ひとりが自らの力を発揮し、価値を生み出せるようにならなければいけないと思うのです。これからは、社員のボトムアップによって発展する会社にしていきたい。私たち自身が原動力となって、井上誠耕園を次のステージに向かわせることができればと考えています。 - 下地
- 私としては、もっと催事販売の回数を増やし、行ったことのない場所にどんどん足を運んでいきたいと思います。らしく園を充実させながら、ご高齢のお客さまや小豆島に訪れることが難しい方には、私たちが催事で会いに行きたいです。井上誠耕園はこれから世界市場の開拓も視野に入れています。これまで以上に多くの方々にお会いするチャンスが増えると思うと、今から大きな期待が膨らみます。
- 武市
- 会社の方針や社長の考えが皆さんにしっかり伝わっているように思うのですが、会社の方向性を知る機会は頻繁にあるのでしょうか。
- 下地
- 月1回の全体朝礼では、必ず社長や経営陣から今後の方針の話があり、全員に共有されます。また、ありがたいことに他の企業に比べ社長や取締役との距離が近い分、直接話をする機会もよくあります。正直、話を聞いた直後は十分に消化できないこともあるのですが、業務を行う中で、「あれはこういう意味だったのか」と点が線になる瞬間があります。
失敗を恐れず、新たなハードルにチャレンジしていきたい
- 佐々木
- 御社は中途採用を強化されていらっしゃいますが、皆さんはどのような方と一緒に働きたいとお考えですか。
- 斉藤
- ボトムアップでやっていくには、現状の社員にはまだまだ経験も知識も不足しています。ですので、今まで培ってきた知見や経験を存分に活かして、失敗を恐れずに新しい風を吹き込んでくれる人に来てもらえたら、と思います。新卒で入社した社員は、この会社のやり方しか知りません。別の会社で経験を積んできた方の経験と発想を織り交ぜて、新たな展開を生み出していきたいです。

- 島本
- 何かを成し遂げたい、と思っている方にきていただきたいですね。営業力の強化、国内店舗の充実、新しいブランドや商品の開発、全国の農家とのネットワークづくり、海外展開など、やるべきことはたくさんあります。新たなことにチャレンジする姿勢のある方に仲間になっていただけたら、とてもありがたいですね。
近年、井上誠耕園の体制も変わりつつあります。現社長から次の世代への継承も意識されるようなタイミングになってきており、理念や想いはそのままに、どのように事業が変化していくのか、楽しみに感じています。そうした中で自発的に事業を推進し、新しい価値を創造したい。そんな意欲をお持ちの方と一緒に仕事ができたらと思います。 - 下地
- 島で暮らしたことのない人は、生活に馴染むまで多少時間がかかるかもしれません。本土への移動手段は船だけですし、会社帰りにどこかで食事、といっても飲食店は決して多くないです。都会と同じような刺激を求めるのは、ちょっと難しいと思います。ただ、日常生活に困ることは全くありません。通勤はマイカーで混むこともなく、出張で満員電車に揺られるたびに、むしろ恵まれているなと実感します。
最も大切なのは、どこに価値を見出すかだと思います。小豆島には、都会にない魅力がたくさんあります。新たな成長のステージを迎えている井上誠耕園で仕事に励み、オフタイムは島のゆったりした時間を味わう。仕事のやりがいと暮らしの快適が両方手に入る、そこが一番の魅力です。
今まで培ってきた経験や知恵を活かし、地域の、日本の農業の未来に貢献したい。そんな方をお待ちしています。一緒に、たくさんのお客さまに会いに行きましょう。 - 佐々木
- 日本の農業を元気にしたい、という理念が現場のみなさんにもしっかり根づいていることを実感し、とても心強く思います。
本日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。
<関連コラム>
<井上誠耕園への応募をご検討の方へ>
「井上誠耕園への応募検討のために必要な情報を得たい」、「今すぐの転職希望ではないが将来に向けて情報を得たい」という方々を対象に、事前相談の機会を設けています。具体的に検討を進めるきっかけとしてぜひご活用ください。

島本 匠
(有)井上誠耕園 第2営業部 部長
小豆島出身。大阪の大学を卒業後、OA機器商社に入社し、営業部門に配属される。その後、情報機器メーカーに転職し、メーカー営業を経験。長男であること、また、都会での生活を通じて改めて島の魅力に気づいたことから、Uターン転職を決意する。2010年に井上誠耕園へ入社。現在は営業部次長として、催事販売・店舗販売・コールセンターの各部門を統括している。

斉藤 仁美
(有)井上誠耕園 営業企画部 渉外広報課・販促企画課 係長
香川県出身。徳島の大学に進学し、農村の活性化や里山再生などについて研究する。学んだ知識を活かしたいと考え、2014年に新卒で井上誠耕園へ入社し、小豆島へ移住。新人時代にはコールセンター業務を経験し、その後企画課へ異動。化粧品の商品開発などに携わる。その後は広報業務に従事し、多くの方に井上誠耕園を知ってもらう機会の創出に取り組んでいる。

下地 和樹
(有)井上誠耕園 コンタクトセンター部 らしく催事課・催事 課長
小豆島出身。中学・高校時代はスポーツに打ち込む。関西の大学に進学し、体育教員やスポーツトレーナーを志すが、島に戻りたいという思いが強まり、大学4年生の秋に就職活動を再開。2018年に、井上誠耕園に入社。現在は催事販売を担当し、日本全国のデパートを飛び回りながら、催事を通じて多くのお客さまに小豆島や自社製品の魅力を伝えている。

佐々木 一弥
(株)リージェント 代表取締役社長
香川県さぬき市出身。大学卒業後、2007年に株式会社リクルートに入社。求人広告の企画営業職として、香川・愛媛にて、四国に根差した企業の採用活動の支援を中心に、新拠点や新サービスの立ち上げも経験。2010年に販促リサーチを行うベンチャー企業の創業メンバーとして参画。創業の苦労と挫折を経験。2012年、株式会社リージェントの創業メンバーとして入社。2019年より代表取締役社長に就任。子どもと焚き火をするのが至福の時間とのこと。

武市 理佐
(株)リージェント コンサルタント
高知県高知市出身。新卒で東京の求人広告会社(リクルートトップパートナー)に入社し、東京都港区を中心に、メーカー・不動産・IT・広告など多岐にわたる業界の大手上場企業からベンチャー企業までを対象に、新卒および中途採用の支援に従事。2017年、「地元・高知のための仕事がしたい」という思いからUターン。大学法人および県庁にて、地域連携や産学官民連携事業に携わる。学生の就職支援や経営者を対象としたビジネスセミナーの企画・運営を通じて、高知で働く魅力創出に尽力。リージェント入社後は、四国全体の地域活性化を目指し、四国へのU・Iターンを希望する求職者に対してキャリア相談や転職支援を行い、四国とのご縁を結んでいる。