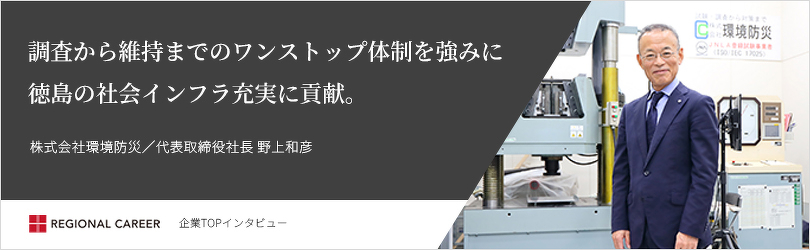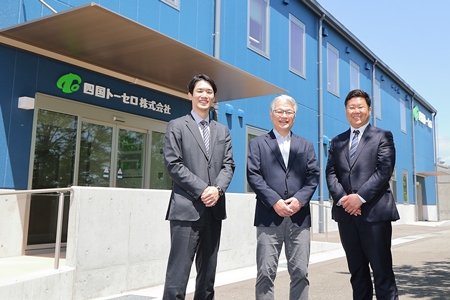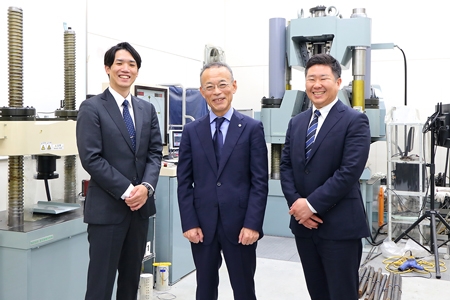建設現場での経験を強みに、建設コンサルタントに転職。
- 德永
- 最初に野上社長のプロフィールを教えてください。
- 野上
- 私は1963年、福岡県の北九州市で生まれ、高校まで地元で過ごしました。それから大阪の大学に進学。大学では橋梁等の土木構造の設計・計算をテーマとするゼミに所属しました。卒業後の1985年、東京本社のゼネコンに就職して大阪支店に配属となり、施工管理、いわゆる現場監督の仕事を担当しました。ヘルメットをかぶり、職人さんと一緒に汗をかきながらものを作る現場は、自分なりにやりがいを感じていましたね。
4年後、私は現場で構造計算・設計を行う必要がありました。現場では建設コンサルタントの方々が構造計算を行い、その結果から作成した設計図をもとに建設を進めるのですが、机上で作成したものとなるため、現場ではそのまま使えない、ということがよくあります。それで施工会社側で現場用の再検討を頻繁に行うのですが、稀に構造計算まで立ち戻る必要も生じます。それを私が、大学卒業後、久しぶりに設計図に向かって電卓を叩きながら構造計算を行ってみると、改めて設計の仕事が自分には合っているな、と実感しました。 - 德永
- その後、生まれ育った九州にUターンされたとお聞きしました。どういった背景があったのでしょうか。
- 野上
- 30代半ばになった頃、そろそろ地元へUターンしたいという思いが少しずつ湧き上がってきました。転職先として浮かんできたのは、これまで勤めていたゼネコンではなく、建設コンサルタントです。好きな構造設計に携わった知識を活かしたかったことに加え、私には建設現場の経験もあります。現場をあまり知らない建設コンサルタントも多い中、現場の実情に通じていることは大きな強みになる、と考えました。
そして1990年、福岡県北九州市が本社で全国に展開していた株式会社福山コンサルタント(以後、福山コンサル)へ転職しました。同社は、公共事業における環境調査や、道路・橋梁・構造物などのインフラの設計などを行っており、私は主に橋梁や構造物の計画、設計に関わる業務を担当しました。 - 德永
- 福山コンサルの持株会社であるFCホールディングスは、御社の親会社ですね。そうした繋がりもあり、環境防災の業務に関わるようになったのでしょうか。
- 野上
- おっしゃる通りです。私の上司が環境防災の社長に就任し、「月1回程度でいいのでサポートして欲しい」とお誘いを受けたことがきっかけで、2014年からグループ企業である環境防災の非常勤取締役を兼務することになりました。その数年後に「野上、君も社長をやらないか」と言っていただきましたが、経営者としては未熟でしたので、自信をもってお答えすることはできませんでした。その後、お二人の代表が継承し、2024年から私が環境防災の社長を引き継ぐことになったのです。

- 吉津
- 全国に展開する福山コンサルから徳島の環境防災に移り、何か違いを感じましたか。
- 野上
- 同じ建設コンサルタントなのでそれほど差はないだろうと思っていましたが、実際に中に入ると、異なる点が多かったですね。ビジネスモデルが大きく違いました。
福山コンサルの主力事業は、交通計画・道路計画・都市計画、それに構造設計や環境調査など建設コンサルタント事業に特化しています。一方、環境防災の場合、それぞれ規模は小さいのですが、部門、分野、商材がとても多彩だったのです。1964年に建設材料試験会社から始まり、材料試験のほか、地質調査、環境調査、水質調査など、地場に根ざしてサービスを拡大してきた会社なので、そのような事業形態になったのでしょう。
“3つの想像力”が顧客課題の解決に不可欠。
- 吉津
- 環境防災の事業上の強みは、どこにあるとお考えですか。
- 野上
- 「環境」分野でいうと、商材、サービスの幅の広さですね。水質調査や土壌調査、最近でいうとアスベストの分析といったことまで幅広く手掛けています。四国を見渡しても、この分野に注力している同業他社は多くないかと思います。これらのサービスはもっと伸ばしていける成長分野だと思います。
「防災」分野では、「徳島、地元をよく知っている」という点が挙げられます。当社には、実際に現場で地質・土質調査を行うスタッフも在籍しています。そういった業務は専門会社に委託する会社も少なくないのですが、当社は自前でできるため、現地で集めた基礎データを分析し、地盤の詳細な特性を踏まえた提案ができます。調査から設計、提案、維持保全までワンストップでできるというのは、大きな強みとなっていますね。
ただし、各分野が連携することで初めて強みになるという感覚が、社員には未だ十分に浸透していない気がします。私が社長に就任してから、社員に対して「ニーズがあったらあまり既成概念に捉われるのではなく、柔軟な発想でアプローチしていこう」と、話すようにしています。調査や設計を行う際、お客さまの持つ情報だけでは十分でない。「こういう調査もやれば、設計がもっと確かなものになります」「こういう調査をしておくと、工期の遅れやコストアップといったリスクが軽減されます」といった視野の広い提案が、当社の強みを活かし、顧客満足にもつながると考えています。 - 徳永
- 社員の方々の意識を変えていくことで、提案力や満足度の向上に繋げていこうとされているのですね。社員の皆さんと直接お話しされる機会は多いのでしょうか。
- 野上
- 徳島に赴任してから、私は正社員・契約社員・派遣社員の隔てなく全社員と面談を実施しました。「単なる愚痴でもいい、固有名詞を出した批判も遠慮しないで。面談で出た話は全て私の胸の中にしまっておくから」と言ってね。すると、働き方や待遇、あるいはキャリアアップ、会社の行く末など、いろいろな意見が出てきました。派遣社員の方からの意見も参考になるものが多かったですね。派遣社員は正社員と違い、俯瞰的な立ち位置で会社を見ることができるからだと思います。そこでもらった意見をもとに、いくつかテーマを決めて、給与、待遇、休日などさまざまなテーマについての改善にあたっているところです。
- 德永
- 面談をする中で、意識して伝えているメッセージなどはありますか。
- 野上
- 社員にはよく、「“対人的な想像力”“独創的な想像力”“未来的な想像力”の3つを大事にしてほしい」ということを伝えています。
「対人的な想像力」とは、相手の立場、考え、事業課題などをきちんと把握すること。商談においても、お客さまが自らの思いを全部言葉にするとは限りません。会話の行間や、表情、心理など、相手の気持ちを推し量る。そこを理解した上で提案を行うと、「環境防災さんはわかってくれている」と信頼につながるのです。
「独創的な想像力」とは、自分なりの知見や工夫、アイデアを提案に活かすこと。これまでの経験だけでなく、そこから来る様々な発想を活かしてほしいということです。
「未来的な想像力」とは、現状だけでなく、この先の社会情勢がどのように変わるのか、提案によって将来どうなるか。そうした未来の姿まで見据えることです。
3つの想像力が定着すれば、先に述べたワンストップの強みを活かした幅の広い提案もできるようになるはずです。 - 德永
- 建設コンサルタントの仕事は専門性の高さばかりに目が行きがちですが、多角的な想像力も必要になってくるのですね。

- 野上
- 建設コンサルタントの仕事に、全く同じ仕事というのは存在しません。お客さまが違えば諸条件も変わります。同じ条件のものを流れ作業でこなせばいい、というケースはまずありません。答えは一つではなく、その時の状況や課題に合わせた解決策を提案しなければなりません。相手の要望や条件を把握し、詳細に調査・分析した上で、「こうした理由があるからこうなんだ、これが最適なんだ」と提示しなければ、当社の提案を選んでもらえないのです。
また建設コンサルタントは、形になった商品を売るビジネスでもありません。お客さまの抱える課題をどうやって解決するか、というサービスを実現することが重要であり、ある意味ではお客さまと一緒になって価値を創り上げる仕事でもあるのです。
そういう提案を重ねていると「次もまた一緒にやりたい」と言われることが増えていきます。顧客の悩みを一緒になって考え、解決しようと努力した成果は、次の仕事を生むのです。心からの困りごとを解決してくれた人に対しては、恩なり信頼なりを感じる。それが人情というものです。
そのために、想像力を働かせて、相手は何を悩み、何を要求しているかをしっかり掴むことが重要です。技術があっても想像力が欠けていれば、本質的な課題の解決はできません。
教育体制の充実で若手人材を育てる。
- 德永
- 今後の課題については、どのように見ておられますか。
- 野上
- 調査・設計に関わる単価のアップ、大手競合との技術競争、官公庁の建設予算の状況などを考えると、受注環境がいっそう厳しくなるのは確かです。そんな中で着実に成長していくには、技術力のアップが欠かせません。既存事業を深堀りしてお客さまとの信頼関係を厚くするためにも、新たな技術領域に取り組むためにも、技術力アップは必要不可欠です。
既存社員への教育により技術の底上げを図り、資格取得を奨励するとともに、キャリア人材の採用で技術力を強化する。さらに当社にない強みを持つ他社とのアライアンスも取り入れる必要があるでしょう。 - 吉津
- 教育面では、具体的にどのようなことに取り組んでおられますか。

- 野上
- 教育に関して言えば、福山コンサルが実施している教育メニューをWebで共有し、勉強会を実施しています。グループ企業のネットワークも活かし、どんどん教育体制を整備していくつもりです。
また、ベテラン技術者の経験や知識を若手に伝承するため、業務カンファレンス・レビューを実行、実践しています。これはベテランと若手が、一緒に図面や調査結果を見ながらどのように分析、判断し、現場に応用していくのか、意見を交換するというものです。経験豊富なベテランの知恵を活かし、若手がぶつかる壁を乗り越えよう、というわけです。
実際の図面や調査結果を前にすると、どういう情報が不足し、どういう調査を提案した方がいいのか、技術的な課題をどう解決するか、具体的に話すことができます。その方が若手も理解しやすいようです。
業務カンファレンス・レビューには、時間が許す限り私も参加するようにしています。自分の専門分野でないレビューもあるのですが、むしろ専門分野でない方が客観的に見られるので、素朴な疑問が湧いてきます。そういう疑問と応答のやり取りから、「こういう専門的表現はお客さまに伝わらない」など、議論が深まるのです。自分がよく知る分野だと、つい「これぐらい分かるだろう」と思い込んでしまうものですからね。
また業務カンファレンス・レビューの際、私はなるべく「これによってお客さまはどんな印象を持つだろう」「これは将来、どんな変化をもたらすだろう」という質問をするようにしています。若手社員たちに、先ほどお伝えした3つの想像力をもって課題にあたってほしいと思うからです。
特に国の事業である公募型提案では、技術提案の評価が重要になります。だから場合によっては一つのレビューに7~8人、行政案件の経験者も含めて、「業務上の課題はなにか」、「こういう提案が必要ではないか」、「別の良い手法や方法はないか」、などと意見を交換します。
公募型提案に長け、実績も豊富な大手も参加するような案件だと、当社を選んでいただくのは容易ではありません。しかし四国で行われる案件の場合は、やはりチャレンジしないわけにはいきません。難しいと思っていても、チャレンジすることが「環境防災は頑張っているな」と次のチャンスにつながることもあります。技術者の意欲を上げ、成長するためにも、チャレンジは大事なのです。
四国には多様な文化、産業がある。
- 吉津
- 野上社長は九州から四国へ、言わばIターンで来られた形ですが、九州との違い、四国の魅力などについてはどう感じてらっしゃいますか。
- 野上
- 九州は、オール九州で一緒に頑張ろうという雰囲気があるのですが、四国は4県それぞれ自立していて、個性がある。その点に面白さを感じます。今後、高速道路など交通網が整備されると、4県の心理的な距離感が縮まり、経済圏や人流も変わるでしょうね。あるいは関西圏と一体となった経済圏と認識されるようになるかもしれません。そうなれば可能性はさらに広がるので、ポテンシャルは小さくありません。
四国で、日本一・世界一というシェアを獲得した製品を持つ会社は、70を超えるそうです。それだけ多様な文化・産業を持っている地域は強いと思います。また、研究開発や設備にも積極的に投資しています。三大都市圏は別として、地方ブロックで比較すると、投資率は全国で2位にランキングします。先行投資に熱心な風土という点も、四国の将来の有望さを語っていると感じます。

- 吉津
- 最後に、四国へのUIターン転職を志向する方にメッセージをお願いします。
- 野上
- 既存事業の深堀りや新規開発を行うには技術力アップが不可欠であり、そのためにはキャリア人材が欠かせません。建設コンサルタント、ゼネコン、あるいは関連する業界で、防災、環境、設計、または営業などの経験を積んできた方を、積極的に採用していきたいと考えています。即戦力となる方に入社いただければ、技術の底上げになるのはもちろん、既存社員にとっても大きな刺激となり、社内が活性化するでしょう。
大都市圏と比べると待遇面が劣ってしまう、という懸念はあるかもしれませんが、会社として対応できることは極力整備していきます。地元に根ざし、地域に貢献できる仕事に一緒になって取り組み、そして共に成長するために、あたなの力をお貸しください。決して後悔はさせません。 - 吉津
- 地元の暮らしや産業を充実させるため、着実、誠実にインフラ整備を進めよう、という野上社長の姿勢に触れることができました。本日はどうもありがとうございました。
当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、(株)環境防災 代表取締役社長 野上和彦氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

野上 和彦
(株)環境防災 代表取締役社長
1963年生まれ。高校まで福岡県の北九州市で過ごし、大阪の大学に進学。大学卒業後、ゼネコンに就職して施工管理として建設現場を経験し、入社4年目の現場において構造検討・計算を担当することになる。大学時代の卒業研究のテーマでもあった構造設計・計算に改めて触れることでその魅力が呼び覚まされた。また、生まれ育った地への社会貢献をしたいという気持ちもあり、1990年に福岡県北九州市に本社を構える、株式会社福山コンサルタントに転職。念願の橋梁を中心とする構造物設計に従事する。それから約四半世紀の2014年、グループ企業である株式会社環境防災の非常勤取締役に就任。さらにそれから10年後の2024年、同社の前任社長の退任を受け、代表取締役社長に就任。

吉津 雅之
(株)リージェント 執行役員
広島県福山市出身。大学卒業後、株式会社リクルートに入社。住宅領域の広告事業に従事し、2013 年より営業グループマネジャーを歴任。2018年に8年半の単身赴任生活に区切りを付け、家族が暮らす四国へIターン転職を決意。株式会社リージェントでは、四国地域の活性化に向けて、マネジメント経験を活かした候補者・企業へのコンサルティングを行っている。

德永 文平
(株)リージェント コンサルタント
香川県高松市出身。大学卒業後、関西の大手鉄道会社に就職。経理部門に配属されたのちに、新規事業セクションに異動となり、自治体と連携したまちづくり事業や、スマート農業事業に従事。幅広い業務の中で、採用担当やチームメンバーの1on1面談を通じて「採用が組織を変えた瞬間」の面白さにはまっていく。「四国ならではの働く価値を創造する」というリージェントのメッセージに、自身も抱えていた悩みの答えを見出し、転職を決意。2024年、株式会社リージェントに入社。現在は自分と同じようにUIターンを検討している方の背中を押すべく、転職コンサルティングに従事している。