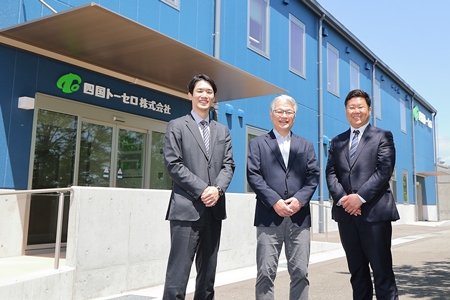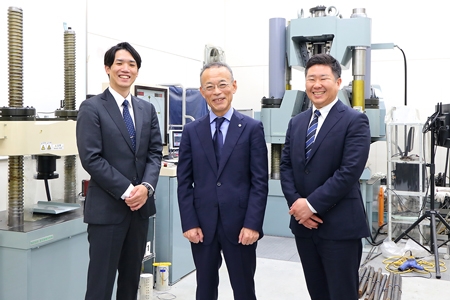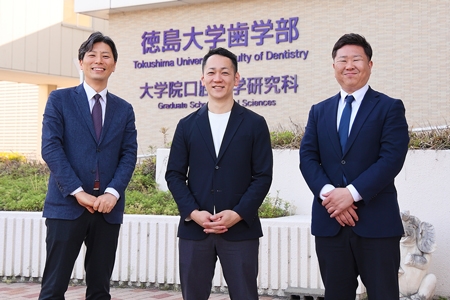世界を知り、己を知る。アフリカでの原体験がもたらした使命。
- 川田
- 最初に、大亀社長のこれまでのご経歴について教えてください。
- 大亀
- 私のキャリアの原点を振り返ると、10代の頃の海外経験に行き着きます。松山で生まれ育ち、中学時代は水泳に打ち込む日々を送っていたため、高校でも地元の進学校に進み、水泳を続けるつもりでした。しかし、父の勧めでスイスの高校を受験することになったのです。正直、あまり乗り気ではありませんでしたが、その決断が私の人生を大きく変えることになりました。

- 川田
- スイスの高校ですか。それは大きな環境の変化ですね。
- 大亀
- ええ。全寮制の学校で、生徒は全員日本人でしたが、教員の半数は外国人で、多様な文化に触れることができました。高校のプログラムで国際ボランティア活動があり、高校2年生の時にアフリカのザンビアを訪れる機会を得たのです。これが私の「原体験」となりました。それまで先進国での生活しか知らなかった私にとって、現地の衛生環境や生活水準は衝撃的でした。しかし、それ以上に心を揺さぶられたのは、決して豊かとは言えない環境の中で、現地の子どもたちが本当に幸せそうな笑顔で暮らしていたことです。広大なサバンナの景色、どこまでも高く澄んだ空、そこで生きる人々の姿に、「豊かさとは何か」「本当の幸せとは何か」を深く考えさせられました。この経験から、漠然とですが「将来はこうした新興国の発展に貢献できる仕事がしたい」という想いが芽生えたのです。
- 川田
- その想いが、家業であるダイキアクシスと結びついていくのですね。
- 大亀
- はい。スイスの高校を卒業した後は、早稲田大学の国際教養学部に進学し、在学中には1年間イギリスへの留学も経験しました。家業を本格的に意識し始めたのは、ちょうどその頃です。ダイキアクシスが株式上場を果たし、次の成長戦略としてインドネシアを皮切りに海外展開を本格化させていました。アジア諸国の水環境を改善するという事業内容を知った時、ザンビアでの経験から生まれた私の個人的なミッションと、会社の事業が完全に一致したのです。点と点が線でつながるように、「自分が人生をかけてやりたいことが、ここにある」と確信しました。
とはいえ、すぐに家業に戻るつもりはありませんでした。一度、外の世界で自分の力を試してみたいと考え、日立製作所に就職し、電力事業部で2年間、営業として勤務しました。そして2018年、満を持してダイキアクシスに入社しました。 - 川田
- 入社されてから社長に就任されるまで、どういったキャリアを歩まれたのですか。
- 大亀
- 入社後は海外事業、経営企画、採用、ITなど、様々な部署を経験させていただきました。社長就任の話を会長である父から受けたのは、突然のことでした。私自身は、会社の70周年にあたる2028年頃だろうと、なんとなく考えていましたが、コロナ禍を経て社会や働き方が大きく変わる中で、会長自身が「もっと早く世代交代し、新しい感性で会社を率いるべきだ」と考えたようです。正直、驚きはありましたが、迷いはありませんでした。「遅かれ早かれ引き受けるのであれば、一日でも早く社長になり、その決断を正解にしてみせる」という覚悟で、お受けしました。
市場そのものを創り上げる「インドモデル」が拓く未来。
- 佐々木
- その強い覚悟は、現在推進されているグローバル戦略にも表れていると感じます。先日公表された新たな中期経営計画(2025-2027)でも、海外事業の飛躍的な成長が大きな柱として掲げられていますね。その中核を担うのが、いわゆる「インドモデル」だと伺っていますが、これは具体的にどのような戦略なのでしょうか。
- 大亀
- 「インドモデル」の核心は、単に我々の製品である浄化槽を売ることではありません。現地の「ルール作り」から参画し、持続可能な市場そのものを創り上げることです。
インドのような新興国では、水処理に関する法規制が未整備な場合が多く、安かろう悪かろうの製品が出回りがちです。実際、我々の製品を模倣した粗悪品が設置され、すぐに機能不全に陥り、悪臭などの問題を引き起こし、なぜか我々に相談が来るといったケースも少なくありませんでした。これでは、現地の環境は一向に良くなりませんし、我々のブランド価値も毀損されてしまいます。
そこで我々が取ったアプローチは、まず現地政府に働きかけ、日本の浄化槽法をベースにした製品の設計基準や性能基準、さらにはメンテナンスの仕組みまで含めた法規制の整備を支援することでした。我々の製品スペックを、インドの公的な規格(日本のJIS規格に相当)に盛り込んでもらうことで、市場全体の品質基準を引き上げ、粗悪品を排除する土壌を作ったのです。 - 佐々木
- それは非常に息の長い、根気のいるアプローチですね。製品を売る前に、まず市場のインフラ整備から始めたのですね。

- 大亀
- おっしゃる通りです。これは、短期的な利益だけを追求していては絶対にできない戦略です。しかし、一度この仕組みが定着すれば、それは他社が容易に模倣できない、極めて強力な競争優位性となります。我々は単なる「メーカー」ではなく、現地の水環境改善を共に進める「パートナー」として政府から認知されるわけです。
この戦略は、実は日本国内での我々のビジネスモデルそのものでもあります。日本で浄化槽ビジネスが成り立っているのは、製品の性能だけでなく、設置や定期的なメンテナンスを義務付ける「浄化槽法」という法律があるからです。我々は、この製品と法律、そしてメンテナンスサービスを一体とした「システム」を輸出しているのです。 - 川田
- なるほど、物理的な製品だけでなく、その価値を最大化する運用インフラごと輸出する戦略というわけですね。
- 大亀
- 現在、この「インドモデル」は着実に成果を上げており、現地法人の売上は2024年度の約6億円から、2027年度には約21億円まで成長し、黒字化を達成する見込みです。今後はこの成功モデルを、インドネシアやバングラデシュ、スリランカなど他のアジア諸国へと展開していきます。
もちろん、だからといって国内事業をおろそかにするわけではありません。むしろ逆です。国内事業が生み出す安定した収益と、そこで磨かれる技術こそが、この壮大な海外展開を支えるエンジンであり、R&D拠点なのです。今後は、環境機器、住宅機器、再生可能エネルギーという国内の3本柱の連携をさらに深め、収益性を高めていく計画です。そして、そこで生まれた新たな事業やサービスを、将来的には海外へも展開していくつもりです。
対話で組織の壁を壊し、部門間のシナジーを加速させる。
- 佐々木
- 社長就任後、組織変革に取り組まれていると伺っています。特に力を入れていらっしゃることは何でしょうか。
- 大亀
- 組織変革は、最重要課題の一つとして取り組んでいます。入社して感じたのは、社会にとって素晴らしい事業を行っているのに、どこかアピールが下手というか、奥ゆかしい文化があることでした。一方、社員は真面目で、組織としてもしっかり機能している。このポテンシャルをもっと引き出したいと思いました。
私がまず着手したのは、徹底した「発信」と「対話」です。先代である父は、現場に大きく権限を委譲し、各事業部がそれぞれの裁量で力強く事業を推進するスタイルを確立していました。そのおかげで各事業部は非常に強固な組織になりましたが、一方で、組織が大きくなるにつれ、事業部間の壁、いわゆるセクショナリズムのようなものも生まれていました。これからのグローバルな成長戦略を考えると、全社が一体となってシナジーを生み出していく必要があります。そのためには、経営層が何を考え、会社がどこへ向かっているのかを、全社員にダイレクトに伝え、理解してもらうことが不可欠だと考えました。 - 佐々木
- 具体的には、どのような取り組みをされていますか。
- 大亀
- まず、社内のコミュニケーションツール(Slack)に自分のチャンネルを作り、自分の考えや日々の気づきなどを発信するようにしています。また、月初めには全社員に向けてオンラインでスピーチを行い、中期経営計画の進捗や理念について語りかけています。
そして、最も重視しているのが「タウンホールミーティング」です。これは、私が全国の拠点に足を運び、若手・中堅社員を中心に10名から20名ほどの小グループで直接対話する場です。会社の現状に対する不満や課題、新しい提案などを、本音で語り合ってもらいます。時には厳しい意見もいただきますが、それこそが現場のリアルな声であり、非常に貴重な情報です。 - 佐々木
- トップが直接、現場の最前線にいる社員と膝詰めで対話する。これは大きな変化ですね。社員の方々の反応はいかがですか。
- 大亀
- これまで経営層と直接話す機会がほとんどなかった社員からは、ポジティブな反応が多いですね。「自分たちの声が経営に届く」という実感は、エンゲージメントを高める上で非常に重要だと感じています。
また、組織改革に向けて、世代間のコミュニケーションギャップという課題にも向き合っています。いわゆる昭和の「背中を見て学べ」という文化で育ってきた管理職世代と、より丁寧なコミュニケーションや明確なフィードバックを求める若い世代との間には、考え方や働き方に対する認識の違いがあります。これはどちらが正しいという問題ではないので、お互いの価値観を理解し、尊重し合えるような研修や仕組み作りを進めているところです。評価制度や人事制度も見直し、頑張った人が正当に報われ、多様なキャリアパスを描けるような組織を目指しています。例えば、全国転勤がネックで採用に至らないケースもあるため、地域限定職の拡充なども検討しています。
地域を愛し、地域と共に成長する。
- 川田
- 大亀社長にとっての愛媛や四国の魅力とは何でしょうか。

- 大亀
- 戻ってきて改めて、愛媛は本当に素晴らしい土地だと感じています。食べ物は美味しいし、海も山も近い。特に松山は都市機能がコンパクトにまとまっていて、生活する上で不便を感じることはほとんどありません。何より、人が温かい。
実は、私と同じように、一度県外や海外に出て、様々な経験を積んでから地元に戻ってきた同世代の経営者や後継者が、ここ数年でかなり増えてきています。10人ほどのグループで定期的に集まっているのですが、「地元をどうにかして盛り上げたい」「もっと面白いことができないか」と、想いを共有していたりします。 - 川田
- それは非常に心強いですね。次世代を担うリーダーたちが、会社を超えて連携し、地域全体の未来を考えているわけですね。
- 大亀
- 東京一極集中は止められない流れかもしれませんが、だからこそ、我々地方にいる人間が、この土地の価値を自ら再発見し、磨き上げ、発信していくことが重要だと考えています。
会社としても、地域貢献には積極的に取り組んでいます。例えば、愛媛マラソンへの協賛もその一つです。ランナーの手荷物袋に、当社の創業者が大切にしていた「スッテモ ムイデモ(何がなんでもやり抜く、の意)」という丹原地方の方言をプリントさせてもらいました。これは、ランナーへのエールであると同時に、我々の不屈の精神と、地域への想いを伝えるメッセージでもあります。

グローバルなキャリアと、四国での豊かな暮らしは両立できる。
- 佐々木
- 我々が日々、転職希望者の方々と接する中で、「地方に行くとキャリアアップが望めないのではないか」「年収が下がるのではないか」という懸念を耳にすることが少なくありません。特に、高いスキルを持つ優秀な方ほど、地方でのキャリアパスが見えづらいという課題があります。大亀社長は、これからの時代における「四国で働く価値」をどのようにお考えですか。
- 大亀
- 私は、「グローバルなキャリア」と「四国での豊かな生活」、この二つは決してトレードオフの関係ではないと考えています。当社のような企業には、その両方を享受できる、これ以上ない環境が整っています。
当社の社員は、松山に暮らしながら、インドやインドネシアの国家規模のプロジェクトに携わることができます。社内には外国籍の社員も多く、日常的に多様な文化に触れることができます。もはや、どこに身を置いているかは重要ではなく、どこを向いて仕事をしているかが問われる時代です。

- 川田
- 地方にいながら、世界とつながる働き方ができるわけですね。
- 大亀
- その通りです。また、高いスキルを持つ人材のキャリアパスが見えづらいという問題は、我々企業側の課題でもあります。これまでは、「そうした人材は地方にはいないだろう」という思い込みから、積極的に募集してこなかった側面があったかもしれません。しかし、今は違います。会社の未来を共に創ってくれるトップレベルの人材には、相応の待遇と、何より大きな裁量とやりがいを提供したいと考えています。
- 佐々木
- それは、UIターン市場にとって非常に大きなメッセージになります。地方には魅力的な経営課題があり、それを解決できる野心的な求人が存在する、と。
- 大亀
- 私は、東京にいるだけでは得られない視点こそが、これからの価値になると思っています。一つの大都市の視点だけでなく、自分が根差す地域社会の当事者としての視点、そして世界市場を見渡すグローバルな視点。この複数の視点を持ち合わせることで、より豊かで、本質的な仕事ができるのではないでしょうか。ダイキアクシスは、そしてこの四国という土地は、そんな新しい働き方と生き方を実現できる、可能性に満ちた場所だと信じています。

- 佐々木
- 本日は、示唆に富むお話を本当にありがとうございました。御社が、愛媛という土地に深く根を張りながら、世界という大きな舞台で挑戦を続ける姿は、多くのビジネスパーソンに勇気と希望を与えるものだと感じました。この対談を通じて、その魅力が一人でも多くの方に伝わることを願っています。
当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、(株)ダイキアクシス 代表取締役社長 CEO・CIO 大亀裕貴氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

大亀 裕貴
(株)ダイキアクシス 代表取締役社長 CEO・CIO
1992年、愛媛県松山市生まれ。スイス公文学園高等部を卒業後、早稲田大学国際教養学部に進学。在学中にイギリスへ1年間留学。2016年に株式会社日立製作所へ入社し、電力事業に携わる。2018年、株式会社ダイキアクシスに入社。海外事業、経営企画、採用教育、IT企画など幅広い領域を統括し、専務取締役などを経て、2024年1月より現職。高校時代に訪れたザンビアでの体験を原点に、世界の環境課題解決に情熱を注ぐ。2023年、早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)修了。

佐々木 一弥
(株)リージェント 代表取締役社長
香川県さぬき市出身。大学卒業後、2007年に株式会社リクルートに入社。求人広告の企画営業職として、香川・愛媛にて、四国に根差した企業の採用活動の支援を中心に、新拠点や新サービスの立ち上げも経験。2010年に販促リサーチを行うベンチャー企業の創業メンバーとして参画。創業の苦労と挫折を経験。2012年、株式会社リージェントの創業メンバーとして入社。2019年より代表取締役社長に就任。子どもと焚き火をするのが至福の時間とのこと。

川田 基弘
(株)リージェント チーフコンサルタント
茨城県牛久市出身。関東の大学在学中に不動産業界、通信業界、社会人訪問インターンなど、数々の業界での就業経験を経て、20歳の時に「1人ひとりの働く価値を創造し、個人が活き活きと働ける社会を実現したい」とキャリアコンサルタントを志す。大学卒業後、日系の組織開発コンサルティング会社に入社。北陸エリアのコンサルティング営業として、大企業から中小企業まで、幅広い企業の事業発展に貢献。子育てをきっかけに妻の地元である四国にIターンを決断。そこで株式会社リージェントの”四国ならではの「働く」価値を創造する”というミッションに深く共感し、キャリアコンサルタントとして入社。現在は愛媛県・香川県を中心に担当し、四国へのUIターンを希望される方への転職コンサルティングに従事。