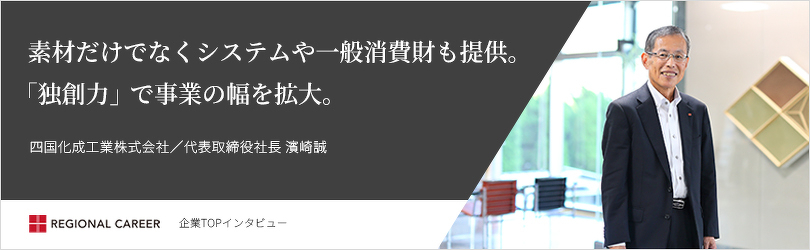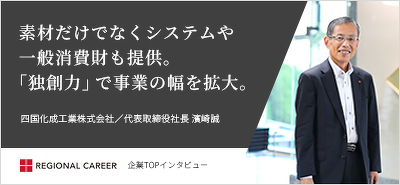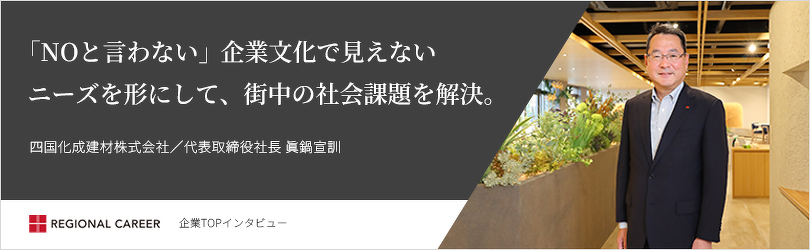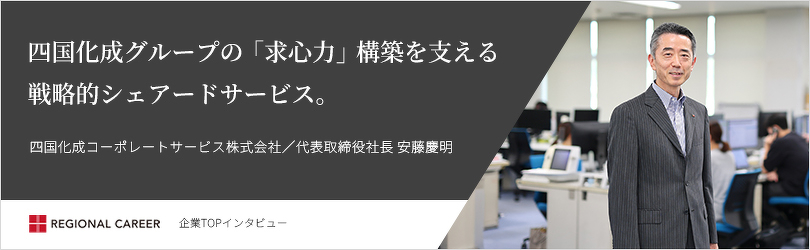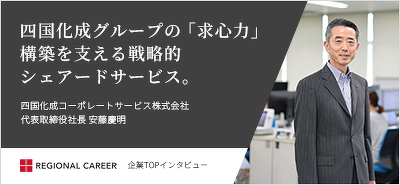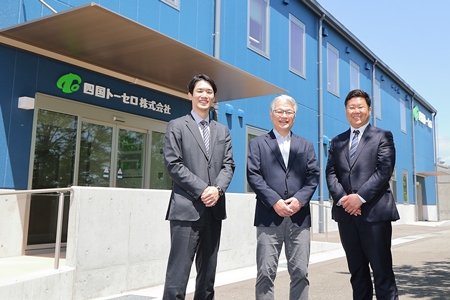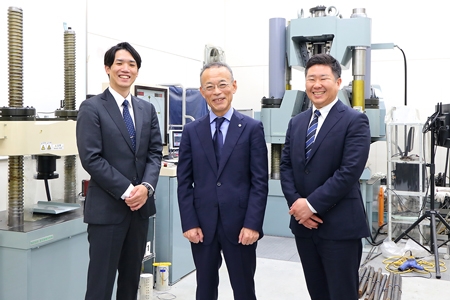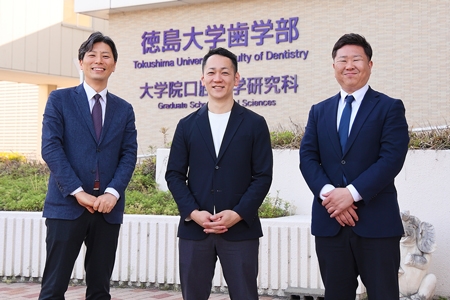それぞれの観点から見た四国化成の特徴
- 溝渕
- まずはプロフィールをお聞きしたいと思います。濱崎社長からお願いします。
- 濱崎
- 私は大学が機械系学科だったので、「就職は機械メーカーだろう」と単純に考え、さまざまなメーカーの説明会や面接に行きました。四国化成に目が留まったのは、まだ化学品部門と建材部門が同居していた頃で、建材のエクステリアなどの設計も面白そうだったからです。四国化成のエクステリア分野にはオリジナル製品が多く、デザイン設計するのに機械系の知識が役立つのではないか、と考えていました。
会社説明会に行ってみると、四国化成の人事の方々は、アットホームな感じで、学生に対してフランクに接してくれる。その雰囲気に魅力を感じたのが、就職のきっかけになりました。
入社後の配属先は、化学品部門でしたが、配属先に行ってもおおらかでした。すごく自由にさせてくれる。出る杭は伸ばす雰囲気が、会社全体に満ちていましたね。
関わった仕事は、化成品の製造をする際の生産設備を設計し、導入・建設に至るまでの全般です。一般のメーカーでは生産技術などと呼ばれる職種になります。
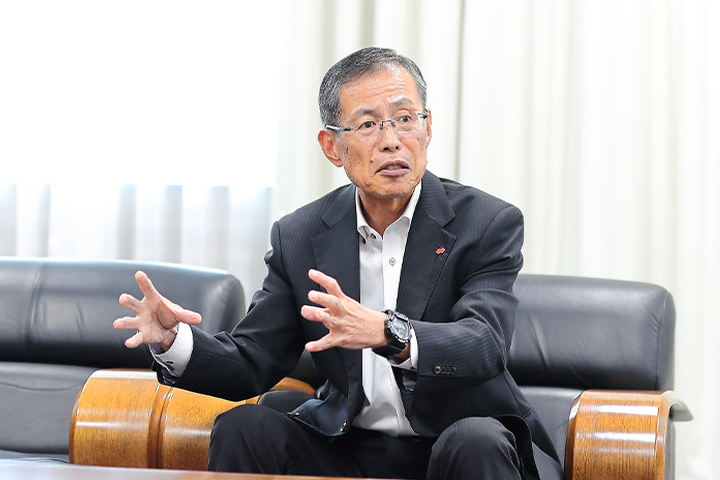
- 溝渕
- 機械系学科を卒業し、化学品部門に配属されるとは思っていなかったのではないですか。
- 濱崎
- 「なぜ化学会社に、機械系学科の出身者が?」と思われることも多いのですが、化学品の製造プラントの建設には、機械系の知識が欠かせません。だから私の部署には、機械工学出身の先輩がたくさんいました。
四国化成の創業期における3大発明である「二硫化炭素」「中性無水芒硝」「塩素化イソシアヌル酸」は、実を言うといずれも後発の製品です。多くの先行会社が存在するマーケットに後から参入してトップに立つことができたのは、生産技術によって独自の製法を生み出したからです。その点で、生産技術は四国化成の土台とも言えます。
ちなみに私は「不溶性硫黄」の生産技術確立に携わりました。個人的には、先の3製品に加え「4大発明」と、密かに呼んでいます。
管理職となってからは、技術部長、工場長など一貫して技術畑を歩いてきました。そして2023年のホールディングス体制移行とともに、四国化成工業の社長に就任しました。四国化成の創業者である多津白年(あきとし)も、生産技術を専門とする技術者でした。今日、いわゆる研究開発系でない、生産技術出身の私が社長となっているのも、不思議な縁だと感じます。 - 溝渕
- 続いて眞鍋社長、お願いします。
- 眞鍋
- 私は1988年に四国化成に入社後、建材部門に配属となり、キャリアのほぼ全般を営業分野で築きました。建材部門で色々な商品が出るたび、カタログを持ってお客さまを訪問していましたが、その際に心がけていたのは、お客さまからの相談に「NOと言わない」こと。上司からは「“できない”とは言わず、どんな話でも持って帰ってくるように」と言われていました。設計事務所や自治体、ゼネコンを訪ねると、当時、エクステリアメーカーがそういったところに営業に来るのは珍しかったので、皆さん興味を持って耳を傾けてくれました。四国化成はアルミを加工するメーカーか、こんなものを作っているのか、と。そこから「こんなことはできるか」「こんな現場があるのだけど、何かできないか」とご相談をいただくようになったのです。私は絶対に「できない」とは言わず、お客さまの要望を持ち帰りました。
- 溝渕
- それらの要望に、うまくお応えできたのですか。
- 眞鍋
- 会社に戻り、お客さまからの要望を社内のいろんな人に伝えると、面白いもので、どうにかできる道が見つかるんですね。四国化成では歯が立たないような仕事も「◯◯という会社に頼んでみるといい」と上司に教えてもらい、行って相談すると何とかしてもらえる。四国化成の建材部門には数々のオリジナル製品がありますが、それらはこういった「知恵を集めて何とかする」という経験から生まれてきたものなのです。
四国化成建材の社長に就任してから、今一度「NOと言わない四国化成建材」をスローガンとして掲げ、全社員と共有しています。お客さまから様々な相談をいただいた時、一緒に考えて答えを導き出す会社でありたいのです。 - 溝渕
- 最後に、安藤社長、お願いします。
- 安藤
- 私は野村證券で31年働いた後、2021年に四国化成に入社しました。
私自身は関西で育ったものの、父方の祖父が愛媛県松山市の出身だったため、松山には親戚がたくさんいました。夏休みには松山に行って、いとこ達と遊ぶのが定番。そういう少年時代を過ごしたので、四国・松山は自分の第2の故郷と思っています。
大学を卒業し、野村證券に入ってから、25年間はずっと大阪・東京を行ったり来たりでしたが、初めて地方転勤になったのが高松支店です。
赴任してから四国に大きな影響を持つ地域の中核企業や有力企業を担当しました。多くの社長とお会いしましたが、私がもともと四国好きなものだから、話が合うのです。「安藤は面白い」「四国のために働いてくれる人が四国に来てくれて良かった」と喜んでくれました。
そういう感じで親交を結んだ中の一社が四国化成です。その縁で四国化成から「うちに来ないか」と誘いをもらい、受けることにしました。 - 溝渕
- 四国化成への転身を決断したきっかけは何だったのですか。
- 安藤
- 私は証券マンとしてIPOなどにも携わりました。その証券マンなりの目利きで、四国化成は伸びしろが大きいと思ったからです。
それなりに規模の大きな会社だと、中にはいろいろ外部の業者をぞんざいに扱うような人もいるものです。しかし、四国化成にはそういう人がいませんでした。嫌なことを言う人もおらず、どの人に会っても良い人ばかりで、とても印象的でした。その点でもいい会社だな、と思いました。
私が四国化成に行くと決めた後、別の大手企業で社長を勤めていた方が「そうか。安藤さんは四国化成に行くのか。じゃあお互い、四国を背負う会社でがんばるってことだな。一緒に四国の発展のために力を尽くそう。」と言ってくれました。私もその言葉を聞いた時、確かに四国を背負って世界に出るのだから、さらに努力しないといけないと決意を新たにしたものです。
四国化成に入社してからは、主に財務を中心に見てきました。分社化により誕生した四国化成コーポレートサービスの社長に就任しましたが、社員にはいつも言っています。
「四国化成の売上の4割は海外マーケットによるもの。言わば“四国”を世界に発信している。これはすなわち、四国へ大きな貢献をしている、ということだ。だから君たちは、自信を持っていいんだ」と。
分社化で意思決定のスピードが上がった
- 溝渕
- ホールディングス体制への移行により各事業会社が誕生して2年になりますが、その変化についてはどのように感じておられますか。
- 眞鍋
- 一番に感じるのは、速度が上がったことです。分社により素早い意思決定や権限委譲が可能となり、現場のやりたいことをすぐ実行に移せるようになりました。また、意思決定がどのような結果につながったかも、見えやすくなったと思います。
- 濱崎
- 分社化以前は、化学品と建材の事業を一つの会社で行っており、一方の事業が芳しく無くても、もう一方が成長を支える、という具合に補完できた面もありました。でもやはり、製品も市場も異なる中で一緒にやっていると、非効率も発生するし、小さな意見・アイデアが上がって来づらくなってしまう。
分社化によって、それらの課題が解消されたと思います。経営判断のスピードが早くなったおかげか、議論が活性化され、新しいアイデアが自由に生まれるようになってきました。事実、この2年で、新たな事業プロジェクトが山のように生まれており、実行段階に入っているものも少なくありません。無論、これまでの積み重ねがあったからこそですが、様々なシーズが、分社化による意思決定の迅速化によってどんどん芽吹き、花開いてきたのです。 - 安藤
- 四国化成工業、四国化成建材というグループの主軸事業会社2社が、自由に羽根を伸ばし、遠心力を利かせて遠くまで飛び立てるようになった。そこに分社化の大きな意義があるように思います。一方、ホールディングスとともに経営管理面を支える、私たち四国化成コーポレートサービスとしては、グループの求心力を保つ存在でありたいと考えています。自らの立脚点が明確であればこそ、各事業会社が大きく翼を広げられるのです。
当社は他の事業会社と取引している立場ですが、そこに上下はなく、リスペクトが大事だと思います。本社だから、ホールディングスだから偉いということはなく、それぞれの役割が違うだけ。お互いにリスペクトしつつ、グループの全体最適を考える。それが私たちコーポレートサービスの役目だと自負しています。

- 眞鍋
- あとは、もっとボトムアップを進めていきたいですね。組織がコンパクトになり、現場の声を経営に反映しやすくなったのだから、自分はどうしたいと思っているのか、それを仕事で実現するにはどうすればいいか、といった声が自然と上がってくるようにしていきたい。そうすれば、もっと主体的に仕事と向き合えるようになるのではないでしょうか。こうすればお客さまが喜んでくれる、社会の人々に貢献できる、とワクワクしながら仕事すれば、必ず良い成果を生むはずです。
自由で、ワクワクする、「もったいない」会社
- 溝渕
- 四国化成はどんな社風、雰囲気を持った会社だとお考えですか。
- 安藤
- 私は外から四国化成を見ていて、ずっと潜在力の高い会社だな、と感じていました。中に入ってみて、その推測は確信に変わりました。現場には優秀な社員が揃っています。
敢えて表現するなら、「もったいない会社」とも言えます。マーケットはニッチで競争相手が少ない、技術力もある、人材も優秀で揃っている。本来はもっと伸びてもいい、それだけの潜在力があると感じます。
上下・社内外の区別なく誰に対してもリスペクトを忘れないという風土、企業文化の良さは残しつつ、ポテンシャルをもっと発揮できるようにしていきたいですね。 - 眞鍋
- 四国化成建材は「未来の暮らしをデザインし、笑顔でくらせる世界の街づくりに貢献する」というテーマを持って事業を進めています。見えないニーズを先取りして形にすることで、社会にワクワクを提供していきたい。そのために大事なのは、私たち自身がワクワクすることです。「NOと言わない」というのも、言い換えれば、どんな課題も前向きにワクワク取り組んでいけば、自分を成長させる糧になる、ということでもあります。
ただ、ここ10年は、新たな課題と向き合う余力がなくなってきているように感じています。これまでは、お客さまのいろんな声を聞き、多彩な製品を作っていった。それによってラインナップが増え、お客さまの悩みを解決できるようになったのですが、今ある製品を作るのに精一杯になってしまっている。
しかし、お客さまの声、要望を見過ごしては、可能性が広がりません。だからもう一度、あるべき姿を見つめ直そうとしています。お客さまに言われたことを、NOと言わずに持って帰ってこいと。原点回帰ですね。これもホールディングス体制に移行し、メッセージを出しやすくなったおかげで浸透しやすくなりました。 - 濱崎
- 私は生産技術としていろいろな製品の開発に携わりましたが、違う会社だったら恐らく日の目をみなかったんじゃないかと思います。上司が口うるさく指示するわけではなく、自分で思うようにやってみる。それについて誰も反対しない。やらせてみて、成果が確かであれば、新人のやったことであろうと偏見もなく採用してくれる。そういう雰囲気がずっとありました。
前向きにやりたいことをどんどんやる、自由に進めていこうという風土は、脈々と受け継がれています。そういった風土が、四国化成の根幹である「独創力」の源泉となっているのだと思います。
私は「情熱」という言葉が好きで、社員にもよく「情熱を燃やそう」と言います。自由にやれるから、情熱も湧くのです。そして情熱を持って取り組めば、どんなハードルも楽しく向き合える。仕事とは本来、楽しくあるべきですよ。没頭している時の充実感、自ら立てた目標に向かってチャレンジする時のワクワク感、そして、苦労の末に成し遂げた時の達成感。それらは仕事の上で、とても大切なものです。この気持ちを、全ての社員に味わってもらいたいと思っています。
社会の課題解決を担う、四国を背負ったグローバル企業
- 溝渕
- 四国化成グループの中期経営計画「Challenge 1000」では、「独創力で、“一歩先行く提案”型企業へ 独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界をリードする」をありたい姿として掲げています。皆さんは、四国化成グループが今後目指すべきはどんな姿だと、お考えですか。
- 眞鍋
- 事業を継続するためには売上を上げ、適正な利益を得る必要があります。しかし、ただ数字を拡大すればいいとは考えません。
人口減社会の中で勝ち残っていくには、独創力に裏打ちされたオリジナリティーを発揮し、市場に認知してもらう、お客さまに頼りにしてもらうことの方が、より大事だと思います。でないと、あっという間に価格競争に飲み込まれてしまいます。たとえ規模は大きくなくとも、ニッチなマーケットでシェアトップを目指す、というやり方が当社には合っています。
ベースにあるのは、「四国化成建材に相談すれば何とかなる」とお客さまに思ってもらえる存在になる、ということです。あの会社、いいもの作ってくれるよね、とお客さまに思ってもらえる。四国化成は何とかしてくれる。社会が抱える課題を解決してくれる。目先の数字を追いかけるのではなく、社会にとって、地域の人々にとって貢献できることを第一義に置く会社でありたいと思います。

- 濱崎
- 私も同じですね。そもそも四国化成の製品は、売上数字を上げるためというより、どうすれば社会の困りごとを解決できるのか、といった思いから事業化したものばかりです。お客さまから言われて気づくのではもう遅い、言われる前に形にしないといけない。そんな認識を、技術者全員が共有しています。まさに“一歩先行く提案”を重視したいのです。
四国化成には大企業のように人が潤沢にいるわけではないので、少ない人数で成果を出していかなければなりません。しかしその分、責任の大きな仕事に早くからチャレンジできました。何度も失敗しましたが、少数だけに徹底的に鍛えられて育ってきたという自負はあります。 - 安藤
- 四国化成の最も重要なパーパスは、「四国を背負っている」ということです。四国を背負っているのですから、四国で一番いい会社にしていきたい。そして四国の価値を世界に広めたいですね。
私は時価総額という視点から、様々な会社を見てきました。「いい会社」は、全方面において本質を見失いません。全方面に対して同じ態度で、しっかりと向き合う。そういう姿勢を持った、四国化成のような会社の価値は高いですよ。時価総額2,000億円くらいを目指せるポテンシャルを秘めている。そういう「もったいない会社」、伸びしろの大きい会社が四国にあるということを、社会にしっかり伝えていきたいと思います。 - 溝渕
- 3人の社長の方々それぞれの考え方、根底に流れる共通する思いに触れることができ、大変心強く感じます。今日はどうもありがとうございました。
当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、四国化成工業(株) 濱崎社長、四国化成建材(株) 眞鍋社長、四国化成コーポレートサービス(株) 安藤社長の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。
<関連コラム>

濱崎 誠
四国化成工業(株) 代表取締役社長
1958年生まれ。1980年、四国化成工業(現・四国化成ホールディングス)に入社。生産技術として、各種製品を製造するためのプラント設計を担当。2002年、技術部長。以後、徳島工場・丸亀工場の副工場長・工場長を歴任。2015年より執行役員。2018年より取締役執行役員。生産・技術本部長、化学品事業本部副本部長を経て、2023年、常務取締役。同年、ホールディングス体制移行とともに、事業会社の一つである四国化成工業(株)の代表取締役社長に就任。ランニングを53歳の時に始め、57歳でフルマラソンデビュー。今も定期的にトレーニングをしている。

眞鍋 宣訓
四国化成建材(株) 代表取締役社長
1988年、四国化成工業(現・四国化成ホールディングス)に入社。建材部門に配属され、営業として多くの顧客のもとを訪問する。当時は「売上目標を持たない、商品提案に専念するだけの営業」を担当したこともあり、建築事務所・ゼネコン・自治体とのパイプづくりに貢献。その努力が、全国の設計事務所・市町村・教育委員会などに必ず四国化成のカタログが置いてある、という状態の構築につながった。2017年に執行役員・建材事業営業統括に就任。以後、一貫して建材事業の営業部門における役職を歴任し、2023年、常務取締役とともに、四国化成建材(株)の代表取締役社長に就任する。

安藤 慶明
四国化成コーポレートサービス(株) 代表取締役社長
父方の祖父が愛媛・松山出身で、親戚が大勢住んでいた関係で、夏休みなどは四国で過ごす。子ども時代の思い出が多い四国の地を「第2の故郷」とも感じている。1990年、野村證券(株)に入社。2015年、高松支店に赴任後、四国に拠点を構える多くの企業を担当。そのうちの一社である四国化成から誘いを受け、2021年に転職。以後、財務部長、企画財務統括、執行役員などを歴任。2023年、ホールディングス体制移行に伴って四国化成コーポレートサービス(株)が誕生し、同社社長に就任。四国化成ホールディングス(株)の取締役も兼務する。