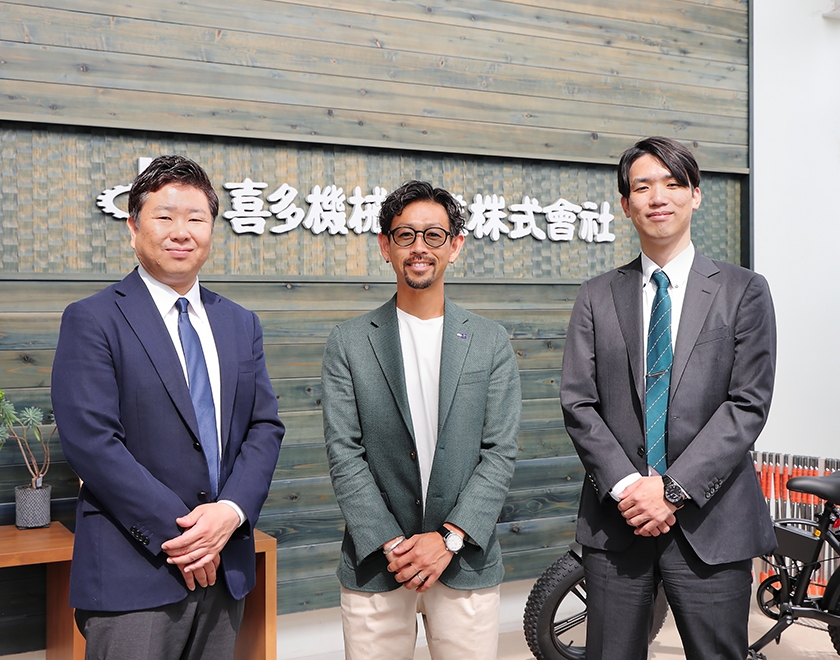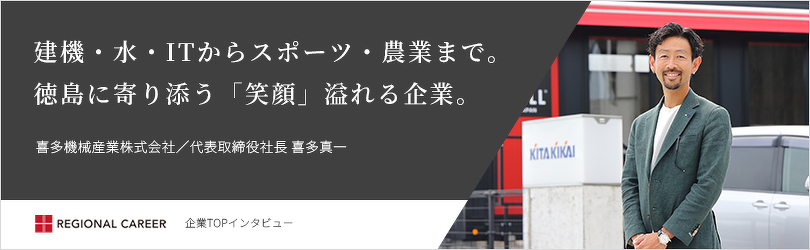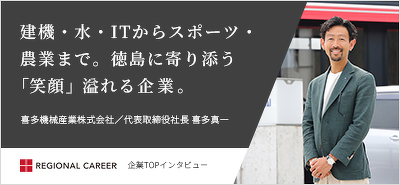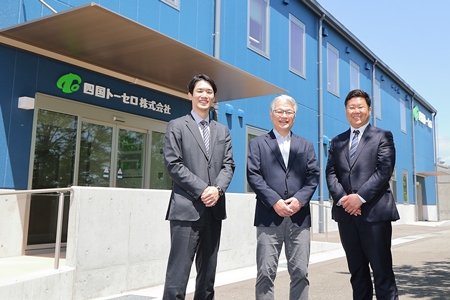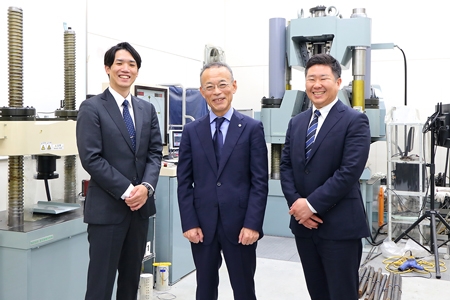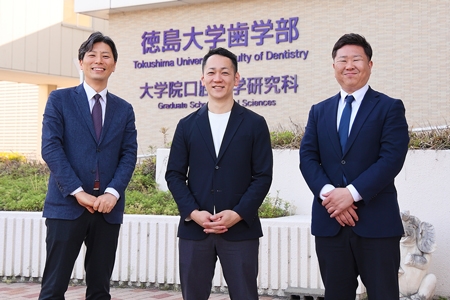フィリピンのプロジェクトを経て、ビジネスに対する考え方が変わった
- 德永
- まずは、喜多社長のこれまでの経歴についてお聞きしてもよろしいでしょうか。
- 喜多
- 高校までは徳島で過ごしました。幼少期からサッカーを続けており、全国大会に出場したこともあります。その後、大学進学を機に関西に出ました。大学在学中に、半年間だけですがアメリカ留学も経験しました。大学4年の前期までに卒業単位をすべて取得し、後期はまるごと休めるように調整してアメリカに渡ったのです。
大学卒業後は、建設機械レンタルを手掛ける「レンタルのニッケン」に就職し、営業職と機械の手配や配送の段取りを行うフロント職を担当しました。宇都宮に配属されたのですが、東日本大震災の影響で栃木も被害がひどく、レンタル業務はかなり多忙でしたね。そこで2年勤めた後、徳島に帰り、かつて祖父が社長を務めていた喜多機械産業に入社しました。
まずは喜多機械産業のことを知ろうと、社内のさまざまな部署を経験していたのですが、その中で開発営業部に所属していた時に、ちょうど始まったのが海外事業です。JICAのプロジェクトに採択され、フィリピンにおける「未電化地域開発普及・実証事業」に取り組もうとしていたところでした。私もプロジェクトに加わり、滝を使った水力発電および飲料用水処理システムを整備するため、フィリピンに赴きました。2ヶ月に1回、2週間くらい現地に滞在してプロジェクトに従事しました。

- 德永
- フィリピンのプロジェクトは、苦労も多かったのではないですか。
- 喜多
- 私は南国の風土も、発展途上国の不便な生活もまったく苦にならないので、暮らしで困ったことはありません。ただ、仕事の面では「定刻通りに人が集まらない」といった問題も発生しました。私たちの滞在期間は2ヶ月に1回、2週間だけです。現地にいないとできないことを2週間でやりきるためにスケジュールを詰め込んでいましたが、予定通りに人が来ないと計画通りに作業が進みません。実際、2週間滞在しても想定していた業務の半分しか完了しないこともありました。現地の担当者に支払い済みの物品が届かず、相手の会社に連絡したところ、そもそもそのような担当者は存在しないことが判明し、詐欺に遭ったこともありました。
そうした大変な思いもしましたが、フィリピンの人々と現場で一緒に汗を流した日々は、とても充実していました。水力発電によって明かりが灯り、飲料水処理システムによってきれいな水が供給されたときに見た現地の人々の笑顔は、今でも鮮明に覚えています。 - 吉津
- 苦労しながら達成感・充実感のある仕事を経験し、何か影響を受けたことはありましたか。
- 喜多
- 前職のニッケンは、ガバナンスやマネジメントが整備された企業でした。それと比べると、喜多機械産業の体制は未熟な部分も多く、「こうすれば利益が残るのに」「こんなことをすれば売上が増えるのに」と、いつも悶々としていました。
しかし、フィリピンの人々に感謝されるインフラを提供できたことで、考え方が変わりました。売上や利益も大切ですが、根本は誰かに喜んでもらうことではないか、と考えるようになったのです。 - 吉津
- それは大きな変化ですね。
- 喜多
- 帰国後に営業本部長に就任したのですが、ちょうどそんなことを思い始めたタイミングだったので、「利益追求第一ではない、人々に喜ばれることをしよう」と発信するようになりました。お客さまが喜ぶことを考えて提案し、対価をもらう。それを積み重ねていけば、数字はついてくる。数字を追うのはもう止めよう。私たちはこの徳島で、10年、50年と地元でお客さまと一緒にやっていくのだから、短絡的に見るのではなく、長期的に考えよう。人とのつながりをこそ大事しよう、と。
- 吉津
- 社員の反応はどうでしたか。
- 喜多
- 戸惑った社員も多かったようで、ベテランの中には「若い本部長が張り切って言い始めた」と苦笑する人もいました。当時の役員や、周囲にいる社長仲間からは「経営はそんな甘いものじゃない」とさんざん説教されましたよ。それでも曲げませんでした。
営業本部長という肩書をもらったものの、私は営業のスペシャリストでもなんでもありません。営業については、社員の方がよっぽど詳しい。私がやるべきことは、社員の邪魔をしないことです。数字を追わせるのではなく、社員がやりたいようにできる環境を整備することです。それで困ったことがあれば、すぐサポートに入る。自分はそのスタイルを貫き通したのです。
いろいろ思いは抱えながらも、そんなシフトチェンジに社員はついてきてくれました。それにより社員との距離が近くなったのを感じます。一枚岩になれたのが功を奏したのか、業績も堅実に伸びてくるようになりました。社員の笑顔も、以前よりかなり増えた気がしています。
自分がやりたいことには、苦しくても笑顔で向き合える
- 吉津
- その後、常務を経て、2021年に社長に就任されましたが、その過程で会社のあり方について考える機会も多かったのではないでしょうか。
- 喜多
- 常務になった頃から、徐々に自分にバトンが渡ってくる実感が大きくなり、「どのような会社にしたいのか」というテーマについて自問自答を繰り返しました。最終的にたどり着いたのは、「社員を笑顔にしたい」という想いでした。
笑顔になるとはどういう時か。例えば、誰かに言われてやらされることは、楽しくありません。ネガティブなことをつい口にしてしまいがちです。
でも、自分からやり始めたことは、何でも楽しいものです。サッカーも、強くなりたいと思えば、つらい練習にも耐えられます。自分の成長を実感できると、達成感が生まれ、楽しさや豊かさも感じられます。
お客さまに営業提案をする際も、自分から前向きに取り組んでいれば、自然と楽しさが湧いてきて、笑顔も生まれます。もちろん、お客さまに対して良い提案ができるようにもなります。良い提案ができれば、それが売上につながり、さらに楽しくなって笑顔になる。やらされるのではなく、自分で決めて行動することが大切なのです。
2017年頃に、何度かヨーロッパへ出張し、ヨーロッパの建設業を視察しました。ヨーロッパの建設業は日本より生産性が高かった為、その理由を確かめに行きました。ヨーロッパの現場では特別高価な機械を使っているわけでもなく、機械はむしろ日本の方が最新式です。なのに、日本より少ない人員で、事故も少なく、高い成果を上げています。
その理由は、現場の作業員が自発的・自律的に動いているからです。日本の場合、現場作業員は常にヘルメットを被り、長袖長ズボンが基本ですが、ヨーロッパでは半袖の作業員も大勢見かけます。彼らは危険な作業をする時だけヘルメットを被り、長袖を着ます。つまり、いつどんな状況で何をしないといけないか、自発的に考えて動いているのです。
今何が必要か自分で判断できるので、オーバースペックなことはやりません。少人数が自律的に動くから、無駄な待ち時間もありません。効率がいいし、イキイキしているし、よく笑顔になっています。端で見ていると、とても格好いいですね。地域の人からも、すごくリスペクトされています。生産性が高いので、当然、給料も良かったようです。
自発的に取り組むと、楽しくなる。笑顔が出る。お客さまや関係者が笑顔になれるサービスを提供できる。そしてお客さまに、地域に選ばれ続ける。そういう会社が、発展しないわけはありません。 - 吉津
- 笑顔で前向きな提案をしてくる社員を見ると、お客さまの満足感も高くなるでしょうね。

- 喜多
- お客さまに「建設機械を貸してくれ」と言われ、「はい、これですね」と差し出すだけなら、何の工夫も楽しみもありません。例えば、「何に使うのですか」と尋ねてみます。すると「新築を建てるので、機械がほしい」というお客さまの思いに触れることができます。「では、最高のメンテナンスを施してお貸しします」とお伝えすれば、お客さまもきっと気持ちよく感じていただけるはずです。その機械が戻ってくる時、「いい機械を用意してくれたから、工期が1ヶ月早く終わったよ」なんて喜ぶお客さまの笑顔に触れることができるかもしれません。そうすると私たちも笑顔になれるし、やりがいや幸福度が上がってきます。
やらされている仕事だと、そうはいきません。お客さまに言われるまま機械を用意するだけです。でも自分から進んでやることで、「いい工事ができた」「工期が短くなった」「いい住まいを建てられた」など、仕事の周辺にある多くの幸せが見つかるのです。そういうことに気づけないのは、もったいないですよ。自分の仕事の広がりを想像することができれば、どんな些細な業務にも自発的に取り組めるはずです。
自発的に取り組むことで、笑顔が溢れる。その行動がお客さまや地域の人々を笑顔にして、地域から選ばれ続ける。私たちは、そういった「笑顔あふれ選ばれ続ける会社」を目指していきたいと考えています。
ローカルでのチャレンジは、大都市より何倍も大きな反響を呼ぶ
- 德永
- 御社は新規事業への取り組みも積極的に行われていますね。
- 喜多
- そうですね。2020年から、プロスポーツ選手も愛用するトレーニング機器「BULL」の販売・レンタルを始めました。きっかけは、私自身がスポーツ好きで、社長就任以降、さまざまなスポーツチームを応援していたことです。
プロを目指すアスリートの中には、学校を卒業し、働きながらトレーニングを積む人もいます。当社もそうした方々を受け入れてきたのですが、プロ候補生の社員には、建設機械の営業を任せるよりも、スポーツ器具の担当を任せた方が、そのポテンシャルを最大限に発揮できるはずです。
そういうことを考えていた時、知り合いの社長に「自社のスポーツ事業を譲りたい」と相談を受けました。じゃあやってみよう、と始めたのです。
日常的にトレーニングしている人の数は、日本の場合人口の3%程度ともいわれています。しかし欧米やオーストラリアだと30%以上にも達します。その意味では、十分に伸びしろはあると見ています。ただ、トレーニング機器は一度購入すると何度も買い替えるものではないため、販売を継続するだけではいずれ頭打ちになるはずです。そこで、コンテナハウスやレンタルといった他の商材・サービスと組み合わせるなど、提供方法を工夫していきたいと考えています。 - 德永
- 新規事業は失敗も多いものですが、御社の場合、あまり失敗例がないようです。これはなぜなのでしょう。
- 喜多
- 新しく何かを始めるときは、必ず成功する方法を徹底的に考え抜きます。どうすれば買ってもらえるか、どうすれば使ってもらえるかなど、さまざまなシミュレーションを行います。
そして、外に出て誰かと話す時は、私はこういうことをやろうとしています、というのをできるだけオープンにしています。そうすると興味を持つ人もいるし、アイデアをくれる人もいる。一緒にやりませんか、という話になる時もあります。自分から発信していると、チャンスに巡り会えるのです。そうしたチャンスをつかんで始めた新規事業が、スダチ農業や林業です。 - 德永
- 農業にも参入されているのですね。どのようなきっかけだったのですか。
- 喜多
- これは、7~8年前から始まった農業機械のレンタルがチャンスを作ってくれました。多くの農家の方々と関わるようになると、「人手が足りなくて、どうにもならない」という声を何度も耳にするようになります。特に、徳島の名産品であるスダチの農家の方々からは、「収穫時期の春夏だけでも人手があると助かる」との声をよくいただいていました。幸い、春夏は建設業の繁忙期が落ち着くため、その時期には社員を派遣してお手伝いしていたのです。
そうしているうちに、社員にも農業のノウハウが身についてきました。そこで、「それなら自分たちでスダチの栽培からやってみよう」と農業事業を始めたのです。毎年栽培面積を10反(約1ヘクタール)ずつ増やす計画を立て、動き始めています。現在も収穫量を増やすために土地を探しています。
徳島名産のスダチも、収穫量はピーク期に比べ2分の1以下まで減少しています。スダチ農家の高齢化も深刻で、平均年齢が80代になる地域もあります。今後さらに収穫量が減少すると見込まれる中で、スダチ栽培を始めたことをお伝えすると、さまざまな方から「ぜひ売ってください」と声をかけられます。ざっと受注残を計算すると、何十トンにもなる。確実にニーズはあるのです。 - 德永
- スダチ栽培が再生すると、喜ぶ方も多いでしょうね。

- 喜多
- こうした事業を行っていると、「徳島のことを本当に大切にされていますね」とか、「さまざまな事業を柔軟に取り入れた、最先端のビジネスモデルですね」と評価してくださる方もいます。しかし、私にとってはどれも当たり前のことばかりです。
大都市圏で同じことをやっても、自分よりもはるかに大きなチャレンジをしている人たちが大勢いるため、それほど目立ちません。しかし、ローカルである徳島では、課題に取り組むことで大きな反響が得られます。ローカルで事業を展開するからこそ、多くの方から感謝され、「誰かの力になれている」という実感が得られると考えています。
どの魅力にもすぐアクセスできるコンパクトさが、徳島の良いところ
- 吉津
- 御社は2026年に創業100周年を迎えますが、100周年に向けて、現在取り組まれていることはありますか。
- 喜多
- 100周年を迎えるにあたり、「売上100億円を目指そう」と目標を掲げ、全員で取り組んでいます。しかし、数字を追うこと自体が目的ではありません。一時的に100億円を達成したとしても、それだけではあまり意味がないのです。事業を永続的に発展させるためには、地域から選ばれ続けることが不可欠です。そのためにも、新たな事業の柱を育てていく必要があります。
100周年からさらにその先の100年を見据えても、売上や会社の規模をいたずらに大きくしようとは考えていません。それ自体が目的ではないからです。
それよりも、社員が退職する時、60歳、70歳、あるいは80歳かもしれませんが、「この会社で働いてきて本当に良かった」と思ってもらえる。そんな会社でありたいと考えています。また、喜多機械産業が徳島にあってよかったと感じてくださる方を、一人でも多く増やしたいとも思っています。 - 德永
- 御社のホームページの株主の項目には「地球」と記載されています。これにはどういった意図があるのでしょうか。
- 喜多
- ベースに豊かな自然がなければ、その上にどれだけいいインフラを構築しても、あるいはどれほど画期的なビジネスモデルを持ってきても、決して成り立ちません。土砂崩れ一つ起こったら、インフラもビジネスも崩壊してしまいます。事業を長期に継続させようと思うと、根っこには自然を守るという発想がなければならない。何かを始める時は、環境負荷はどれくらいか、ということが当たり前のように話題に上らないといけない。そういう状況を作りたいと思い、「株主は地球」というメッセージを発信しました。
- 德永
- ダイバーシティも大事にされているようですが、どのような背景から力を入れておられるのですか。
- 喜多
- 私はスペシャリストではないので、わからないことはすぐスペシャリストに聞きに行きます。人に話を聞く、ということは、その意見を受け入れる、ということです。せっかく専門的な見地から意見を言ってくれたのに「それは違う」などと否定していたら、私に意見やアドバイスを提供してくれる人がいなくなってしまいます。だから、まずは全てを受け入れよう、という態度を大事にしたいと考えています。
既に述べた通り、上からの指示がないと動けない人よりも、自分で考えて動く集団の方が強くなります。自分で考えて動けるのは、確固たる個性があるからです。その個性を受け入れ、認めなければ、自発的な動きなどできるはずがありません。だから多様性を重視しているのです。
世界に行くと、周りの目なんて気にせず、どんどん自己主張してくる人がたくさんいます。むしろその方がスタンダードなのかもしれません。その分、しっかり仕事をする。髭を生やしピアスをしていても、仕事には誰よりも真剣に取り組む。性別も世代も個人的特徴の差異も一切関わりなく、自分のスタイルを大切にして、自発的に自身の役割と向き合う。それでいいと思います。だから社員には、もっと自分のやり方や発言、行動に自信を持ってほしいですね。

- 吉津
- 私たちは「四国ならではの働く価値を創造する」というミッションを掲げて事業活動を行っています。喜多社長は「四国・徳島ならではの価値」について、どのようにお考えですか。
- 喜多
- 徳島は、とてもコンパクトな地域だと感じています。私はサーフィンが好きでよく出かけるのですが、空港からこれほどサーフポイントが近い地域は珍しいですね。徳島市内には海も山も川もあり、自然が豊かで、アウトドアレジャーをたっぷり楽しむことができます。ゴルフ場も車で15分もあれば行けますし、県庁の目の前にはヨットハーバーもあります。自然が豊かなので、食べ物もおいしい。15分程度であらゆるレジャーにアクセスできる場所は、全国的に見てもそう多くはないと思います。
休日の朝に起きて、「今日は何をしようか。川に行ってみよう。」と思ったら、すぐに実行できるのはとても良い環境だと思います。朝一番でサーフィンをしてから会社に出勤する、そんなことも可能です。こうしたコンパクトさは徳島ならではの特徴であり、自然の豊かさを感じながら生活できることが大きな魅力だと感じています。これからも私たちは自然をベースとして、地域に貢献できる事業を展開していきたいと考えています。
当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、喜多機械産業(株)代表取締役社長 喜多真一氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

喜多 真一
喜多機械産業(株) 代表取締役社長
1989年、徳島生まれ。小学生の頃からサッカーを始める。大学の在学時、半年間のアメリカ留学を経験。帰国後に建設機械レンタルの(株)レンタルのニッケンに就職。栃木県に配属され、営業職・フロント職に従事する。2013年、徳島にUターンし、喜多機械産業(株)に入社。JICAに採択されたフィリピンにおける「未電化地域開発普及・実証事業」プロジェクトのメンバーとなる。その経験を踏まえ、「笑顔あふれ選ばれ続ける会社」という企業哲学を発信するようになる。帰国後、営業本部長、常務を歴任し、2021年に代表取締役社長に就任。数多くの新規事業を手がける一方で、社内教育制度KTLA開校、ダイバーシティのための環境整備などにも力を入れている。

吉津 雅之
(株)リージェント 執行役員
広島県福山市出身。大学卒業後、株式会社リクルートに入社。住宅領域の広告事業に従事し、2013 年より営業グループマネジャーを歴任。2018年に8年半の単身赴任生活に区切りを付け、家族が暮らす四国へIターン転職を決意。株式会社リージェントでは、四国地域の活性化に向けて、マネジメント経験を活かした候補者・企業へのコンサルティングを行っている。

德永 文平
(株)リージェント コンサルタント
香川県高松市出身。大学卒業後、関西の大手鉄道会社に就職。経理部門に配属されたのちに、新規事業セクションに異動となり、自治体と連携したまちづくり事業や、スマート農業事業に従事。幅広い業務の中で、採用担当やチームメンバーの1on1面談を通じて「採用が組織を変えた瞬間」の面白さにはまっていく。「四国ならではの働く価値を創造する」というリージェントのメッセージに、自身も抱えていた悩みの答えを見出し、転職を決意。2024年、株式会社リージェントに入社。現在は自分と同じようにUIターンを検討している方の背中を押すべく、転職コンサルティングに従事している。