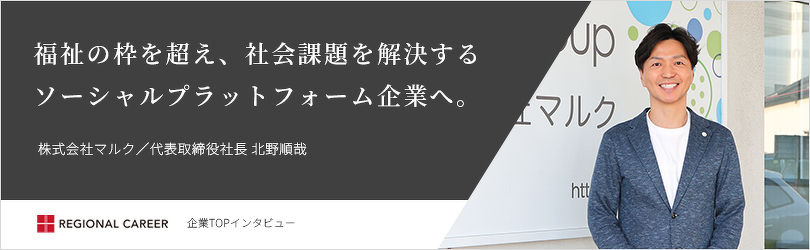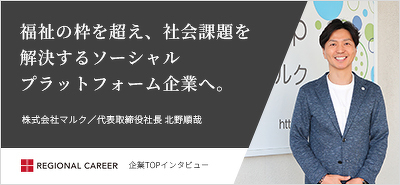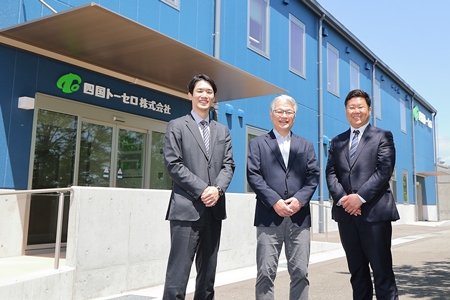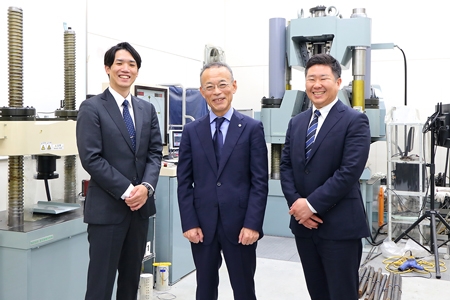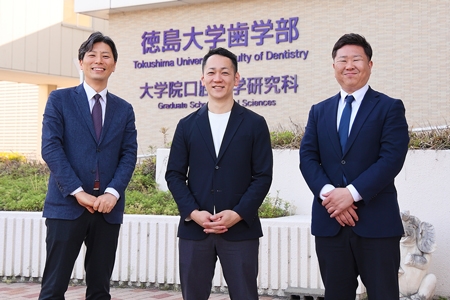経営理念“解散する”に込めた哲学
- 佐々木
- まず初めに、経営理念である「強さと優しさが循環する社会の実現をもって解散する」に込められている想いを教えてください。
- 北野
- 弊社は2006年に私の兄が創業したのですが、兄が経営理念にあえて「解散する」というフレーズを入れたのです。その真意を端的に言えば、我々の最終的な目標を示すものですね。いつか障がいのある方が当然のように社会で活躍できる世の中が訪れれば、極端な話、我々のような事業者は必要なくなる。つまり、我々が目指す理想の社会が実現した暁には、マルクは解散して良い、という逆説的な意味で「解散する」を掲げています。それが我々の定める最終ゴールなのです。
実は2019年に株式を上場する際にも、「企業は永続的に成長していくものだ」という観点から、この「解散する」が経営理念に入っていることを疑問視する声が一部で上がりました。しかし我々としては、先ほど申し上げたように、この言葉はあくまで目指す社会像を示したものだと説明し、最終的には理念に残しています。兄から受け継いだこの理念を、私自身も常に経営の軸に据えておりますし、社内でも事あるごとに理念に立ち返ってメッセージを発信するよう心がけています。

- 佐々木
- 目指す理想の社会像とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
- 北野
- 一言で言えば、「強さと優しさが循環する社会」を実現したいと考えています。障がいのある方々が社会で活躍し、お給料を得て、納税し、消費する。そうすることで、これまでは社会保障の支援を受ける立場だった人たちが、社会を支える側に回っていきます。そして、そこで生まれた新たな経済的活力が、今度は他の支援を必要とする人たちにも巡っていく。これが「強さと優しさの循環」という言葉に集約されています。
- 佐々木
- その理念は、揺るがない御社の根幹を成すものなのですね。
- 北野
- そうですね。私が創業者からバトンを受け取った時、この会社をどのように進めていくべきか改めて深く考えたのですが、その時に立ち返ったのもやはり経営理念でした。100年後には今の我々は誰もいないでしょうし、事業の形も社会のあり方も変わっているはずです。そんな中でマルクという会社が残っているとしたら、変わらないものは何か。それが経営理念だと気づきました。逆に言えば、この理念が変わってしまえば、それはマルクでなくても良いということになります。ですから、私自身、常に経営理念を自身の経営スタイル、経営方針の軸に据えています。この「解散する」という目標が、常に新しい課題に挑戦し続ける原動力になっているとも言えるかもしれません。
IPOの意義と、伝えたかったメッセージ
- 佐々木
- 先ほど少し話題に上がりましたが、御社は2019年3月に東証TOKYO PRO Marketへの上場を果たされました。IPOに踏み切った狙いや、その後の社内外への影響について教えていただけますか。
- 片山
- IPOの目的として、一般的には資金調達が第一に挙げられますが、我々の場合はそれ以上に大きな目的がありました。それは「メッセージの発信」です 。当時、我々が上場を目指した時点では、就労継続支援事業で上場している企業はありませんでした。厳密に言えば、就労移行支援というスクール型の事業での上場企業はありましたが、我々のように障がいのある方を雇用して共に働く障がい者就労継続支援事業として日本初の上場だったのです。
当時、従業員約150人のうち110人、つまり7割以上が障がいのある従業員でした。そのような会社が株式上場を果たす。その事実を世の中に発信することに大きな意味があると考えていました。そのため、上場セレモニーで鐘を鳴らす際には、障がいのある従業員の方にも代表して打鐘してもらいました。東京証券取引所は当時110年の歴史がありましたが、障がいのある方が鐘を鳴らしたのは歴史上初めてのことだったそうです。

- 佐々木
- それは非常に象徴的なシーンですね。北野社長はその瞬間にどのような願いを込められたのですか。
- 北野
- 障がいのある方が、これからもっと社会に進出し、自立し、戦力として受け入れられていく。そうした未来を強く願いました。世の中の障がい者雇用の現状や、障がいのある方に対する見方に一石を投じることができるのではないかと。例えば、私たちの上場を知った企業が「うちも障がい者雇用に取り組んでみよう」と思ってくれるかもしれない。あるいは、同じような支援事業者が「頑張れば、自分たちもあの舞台に立てるかもしれない」と希望を持ってくれるかもしれない。そして何より、現場で働く障がいのある方々が、「自分たちは誇れる存在なのだ」と自覚し、自信を持って社会に出ていくきっかけにしてくれるかもしれない。そういった波及効果を期待していました。
私たちが目指す社会の実現には、途方もない時間がかかるでしょう。それでも、こうした象徴的な出来事を積み重ねていくことで、間接的にでもそのゴールに近づけるのではないかと考えたのです。IPOは、そのための手段のひとつでした。 - 佐々木
- IPO後、具体的にどのような影響がありましたか。
- 片山
- まず、採用が大きく変わりました。特に新卒採用は、それまでの2~3倍になりましたね。これは、上場による信用力の向上や、私たちが発信してきたメッセージ性に加え、学生の親御さんの反応が変わったことが大きいと思います。特にUターンして愛媛に帰ろうというケースでは、ご家族の理解がとても重要です。「地元に帰って本当に大丈夫か」「どんな会社に就職するのか」と心配されがちですが、「上場企業だよ」と説明できることは、学生さんにとっても親御さんにとっても、心理的なメリットが非常に大きいと感じています。
また、IPOで調達した資金は、我々の成長戦略を具体的に進める上で大きな力となりました。例えば、関東での新たな事業所開設などは、この資金を活用して実現したものです。これは、我々が2015年から10年間のグループビジョンとして掲げていた「福祉事業所から社会企業への成長」という目標達成に向けた、具体的な一歩となりました。
プラットフォーム化で挑む、新たな社会課題の解決
- 佐々木
- 現在、御社では10年ビジョン「福祉事業所から社会企業への成長」に続き、「ソーシャルプラットフォーム企業への進化」を掲げていらっしゃいますね。これについても詳しくお聞かせいただけますか。

- 北野
- 上場後、事業所数や社員数の増加に伴い、さまざまなステークホルダーの方々との対話が広がる中で、障がい者福祉にとどまらず、社会全体の課題にも視野を広げるべきステージに来たと感じるようになりました。こうした背景から、次の10年では、貧困や虐待、フードロスといったさまざまな社会課題を解決するプラットフォーム企業への進化を目指しています。あくまでも障がい者福祉に軸足を置きつつ、少しずつその他の多様な社会課題の解決にも取り組んでいける、そんなソーシャル領域に特化した企業グループに成長していきたいと考えています。
- 佐々木
- 具体的にはどのような成長戦略を描いていらっしゃるのでしょうか。
- 北野
- 一つ目はオーガニックグロース、つまり就労支援施設や放課後等デイサービス事業所などの出店拡大です。現在、全国で20拠点を展開していますが、これを30拠点、40拠点へと順次拡大し、当社の支援を届けられる地域や利用者の裾野を広げていきたいと考えています。着実に自立・就労につながる支援を積み重ねていくことで、「マルクがやりたいこと」を世の中に広めていく狙いです。
二つ目はM&Aによる成長です。福祉業界は今、制度改正や最低賃金アップなどの影響もあって経営が厳しくなっている事業者も少なくありません。そうした中で業界再編や事業者間の統合・集約が進みつつあります。そこで、地域で頑張っている事業者の方々に当社グループの仲間になっていただくことで、一つの大きな船のような規模になり、社会保障費が減少していく中でも安定して事業を継続できる体力を持てるようになりたいと考えています。M&Aの積極活用は今後の重要な選択肢ですね。
そして三つ目がプラットフォーム戦略です。我々自身が新たに直接出店するだけでなく、自社の持つノウハウやプログラムを提供することで業界全体の底上げを図っていこうという取り組みです。その代表例としてサブスク型のプログラム提供サービスがあります。全国には約2万か所もの放課後等デイサービス事業所がありますが、そこに当社が開発した療育プログラム教材を提供しようと考えています。例えば、小学校卒業までしか通えなかった子どもたちに、中学・高校まで継続してサービスを提供できるようになるのです。そうすれば、その子たちは社会に出るための力をより一層身につけられるかもしれない。また事業所側にとっても、支援年齢の上限が引き上がることで利用者が長く通ってくれるようになり、経営の安定につながるメリットがあります。これは自社拠点を増やすだけでは届かなかった層にもリーチできる、新たなアプローチだと考えています。 - 佐々木
- 他の事業者のサービス提供を裏側から支援していくわけですね。
- 北野
- そうですね。もちろん直接出店も引き続き進めながら、M&Aによるグループ拡大も図りつつ、それに加えてこのプラットフォーム戦略で事業の幅を広げていきたいと考えています。また、障がいのある方の雇用を創出するための転職支援ビジネスの構想もあります。例えば、単に企業と求職者をつなぐ転職サイトではなく、事業所側が自ら求職者の情報を登録し、AIが間に入ってレコメンドしてくれる仕組みもいずれは可能になるのではと考えています。今はまだ構想段階ですが、ゆくゆくは日本の障がい者雇用の仕組みそのものをオンライン上で完結できるようなサービスが作れたら面白いですよね。また、福祉以外の社会課題にも挑戦したいという想いがあります。実際に子会社を通じた食品ロス問題への取り組みなども進めています。
- 佐々木
- そうした取り組みの一環で、オンラインでの研修サービスも始められたと伺いました。
- 片山
- オンライン研修事業は、福祉事業所を運営する上で必要な「サービス管理責任者」という資格をオンラインで取得できる講座を提供しているのですが、非常に好評で、開始からまだ1年経たない段階ですが早くも事業の柱に育ちつつあります。従来は各自治体が年に1回程度リアルで開催していた研修をオンライン化することで、場所や時間の制約をなくし、毎月開催できるようにしました。これにより、全国に約15万ある事業所のニーズに応えることができます。これらの事業を通じて、給付金だけに頼らないビジネスモデルを構築し、経営理念の実現に近づけていきたいと考えています。このような多角的なアプローチこそが、より広範な社会課題の解決に貢献する道につながり、マルクを真の「ソーシャルプラットフォーム」へと進化させていくと信じています。

四国だからこそ味わえる仕事のやりがい
- 佐々木
- 北野社長は愛媛のプロバスケットボールチームの球団社長も務めていらっしゃるいますよね。
- 北野
- そうですね。2023年、愛媛県をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「愛媛オレンジバイキングス」の球団社長に就任しました。これは自分が生まれ育った町に何か恩返しがしたい、自分の経験やスキルを地域に還元したいという想いからです 。私は、これまでのキャリアで培ってきた知見を、故郷やゆかりのある地域に還元していくことに大きな価値があると考えています。それは、その町に生まれた方、その町をよく知る方にしかできない役割だと思います。
例えば、都会で長く暮らしていた方が久しぶりに帰省した際、昔賑わっていた商店街がシャッター通りになっているのを見て寂しさを覚えることがあるかもしれません。そうした時に自分の力を故郷のために活かせないだろうかと考える。自分の手で故郷をもう一度元気にしたい、今そこに住んでいる子どもたちが未来に希望を持てるような町にしたい。そうした想いを実現できることが、生まれ育った町で働く醍醐味の一つだと考えています。 - 佐々木
- 確かに、ゆかりのある土地への想いがあるからこそ、特別なやりがいを感じられるのかもしれませんね。
- 北野
- その通りです。そして、四国で働くことは、決してキャリアの減速ではありません。四国には人口減少などの課題もありますが、その分、新しい挑戦の余地が広がっているフィールドでもあります。都市部ではなかなか携われないような社会課題に対して、四国だからこそダイレクトに取り組んでいける面白さがあります。当社も愛媛で創業し、四国発の企業として上場まで至りましたが、地方にいながらでもこれだけ挑戦できるということを示せたのではないかと思っています。
Uターン・Iターンを検討されている方がいらっしゃったら、「四国には面白い会社や社会の役に立てる仕事がたくさんある」とお伝えしたいですね。

- 佐々木
- 片山さんは、四国で働く価値についてどのようにお考えですか。
- 片山
- 私は12年前に地元の愛媛へUターンで戻ってきました。当時は転職先を見つけることに苦労しましたが、運良くマルクに出会えて、これほどまでにやりがいのある仕事が地元にあったのかと驚きました。最初は業界知識もゼロの状態で飛び込みましたが、さまざまな方と関わる中で日に日に視野が広がっていきました。今では、自分の仕事が社会の役に立っていると実感しながら働くことができています。地元で頑張りたいという想いがある方は、恐れずにチャレンジしてみてほしいですね。四国にはあなたの力を必要としている会社や人々が必ずいますし、働くことで地元に恩返しもできる。そんな喜びを、ぜひ味わってもらえたらと思います。
- 佐々木
- お二人の言葉からは、事業への強い想いや四国というフィールドで働くことの意義が伝わってきました。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。
当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、(株)マルク 代表取締役社長 北野順哉氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

北野 順哉
(株)マルク 代表取締役社長
愛媛県松山市出身。松山大学を卒業後、流通企業や広告代理店でキャリアを積む。2013年、兄が代表を務める、まるく株式会社(現:株式会社マルク)に入社。2015年、同社代表取締役社長に就任。「福祉事業所から社会企業への成長」というビジョンを掲げ、当時愛媛県内で3か所の福祉事業所を運営していた同社を、就任からわずか4年で株式上場へと導く。現在は全国20か所の事業所を運営するとともに、サブスクリプション型の療育事業やオンライン研修事業を展開し、既存の福祉制度の枠にとらわれない新たなビジネスモデルの構築を推進。2023年にはプロバスケットボールチーム「愛媛オレンジバイキングス」を運営する株式会社エヒメスポーツエンターテイメントの代表取締役社長に就任し、スポーツ経営を通じた地域活性化にも取り組んでいる。

片山 正人
(株)マルク 取締役管理部長
愛媛県松山市出身。大学卒業後、サービス業でキャリアを積む。2009年9月にまるく株式会社(現:株式会社マルク)に入社。就労支援の現場でさまざまな業務を経験した後、新規事業として立ち上げたスコラ事業(現:放課後等デイサービス事業)で一号店の開業準備に携わる。その後、就労支援事業部の部長に就任し、現在は管理部部長に着任。適時開示・コーポレートガバナンスの内部監査など、主に上場企業に求められている開示業務に従事している。

佐々木 一弥
(株)リージェント 代表取締役社長
香川県さぬき市出身。大学卒業後、2007年に株式会社リクルートに入社。求人広告の企画営業職として、香川・愛媛にて、四国に根差した企業の採用活動の支援を中心に、新拠点や新サービスの立ち上げも経験。2010年に販促リサーチを行うベンチャー企業の創業メンバーとして参画。創業の苦労と挫折を経験。2012年、株式会社リージェントの創業メンバーとして入社。2019年より代表取締役社長に就任。子どもと焚き火をするのが至福の時間とのこと。