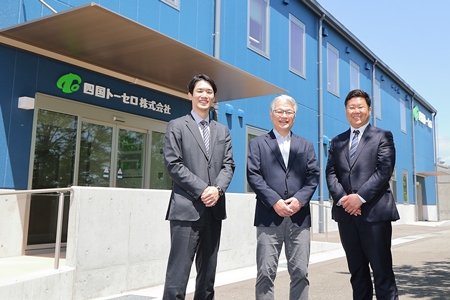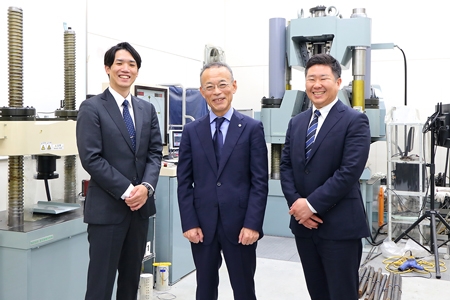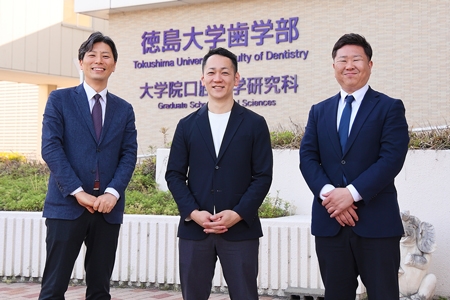売上の大半をオリジナル製品で占める。
- 佐々木
- 最初に重見さんのプロフィールを教えてください。
- 重見
- ずっと愛媛で育ち、大学も愛媛でした。学んだのは機械工学です。就活では自動車関係のメーカーなども検討しましたが、最終的に興味を持ったのはアテックスでした。実家が農家で、昔から同社の運搬車を使っていたのです。私も農作業を手伝いながらそばで見ており、農業に欠かせない機械であることはよく分かっていました。それが入社のきっかけとなりました。
研究開発部に配属され37年。ずっと開発だったので、アテックスで販売している全ての製品に何らかの形で関わっています。入社当時の主力は農作業用の運搬車で、他に大手農機メーカーのOEM製品を手掛けていました。草刈機や堆肥散布車はまだなく、電動車いす「マイピア」については、ちょうど開発を始めたタイミングでした。

- 佐々木
- 農作業用中心だったアテックスにとって、電動車いすは他領域の製品です。会社にとっては、大きなターニングポイントになったのではないでしょうか。
- 重見
- 当時、介護用の電動車いす自体はあったのですが、手押しの車椅子にハンドルがついた程度。病院だけで使うもので、一般の元気な高齢者が好んで乗るイメージはありませんでした。そこで当時の技術者たちは、普通の人でも乗りたくなる、おしゃれで快適な電動車いすを作ろうと考えたのです。
なぜ電動車いすを?と思われるかもしれませんが、農業には多くの高齢者が従事しています。中には山間部に田畑があり、坂道の昇り降り苦労する人も大勢います。そんな姿に触れていたことから、電動車いすにたどり着いたわけです。農機具も電動車いすも、ユーザーが共通していたことが、ヒントになりました。そして「マイピア」が誕生しました。一般向け電動車いすを最初に世に出したのは、実はアテックスなのです。 - 佐々木
- マイピアの生産開始が1988年。その後草刈機も開発されていますね。
- 重見
- 斜面で使う歩行型の草刈機「タスカル」は、1997年に生産を開始。これはもともと大手農機メーカーから開発依頼を受けたもので、OEM製品として発売しました。タスカルも、初めて世に出た製品の一つです。
この経験をベースに、次は乗用の草刈機を開発しました。乗用草刈機は既に先行品が存在し、値引き競争に入っている段階でした。そんな状況であえて参入を決めたのは、古くから付き合いのある青森の販売店から「値引き競争をしなくていい、独自性のある乗用芝刈機を開発してほしい」と要望を受けたからです。
早速、当時の研究開発部長が青森に飛び、現場を視察しました。するとあることに気づきました。草刈機は果樹園で使用するのですが、木の根本の雑草を刈るには、木の枝を避けながら運転しなければなりません。しかし木の枝を体の動きだけでよけるのは、大変な手間です。そこで部長は「運転席の椅子が横に動けば、枝を避けやすくなる」と考えたのです。特許も取得したこの機構を搭載した乗用草刈機「刈馬王」は、2005年にリリースしました。 - 佐々木
- 草刈機は順調にバリエーションが増えていった、とお聞きしています。
- 重見
- 乗用型の後に、歩行型草刈機を改良。タイヤ式を止め、クローラ、いわゆるキャタピラ式に変更したのです。これは、休耕田が増えていたという事情があります。休耕田とは言え、雑草を放っておくと、耕作中の近隣の田んぼに迷惑をかけます。休耕田は水はけが悪いので、草刈り中にタイヤが土にはまって動けなくなる…といったことが起こっていたのです。しかしクローラであれば、土が悪かろうが斜面だろうが、どんどん進んでいけます。このクローラ式の歩行型草刈機も、当社が初めて出した製品です。
- 佐々木
- お客さまが使用されている場面を見て、製品を改良されたのですね。
- 重見
- さらに発展させたのが、2019年に生産を開始したハイブリッドラジコン草刈機「神刈」です。草の生い茂る場所に入っていくと、急に蛇が出てきたりします。そうなると、嫌がる作業者もいますよね。じゃあラジコンですれば、怖い思いをすることもなく、安全に作業できるのではないか…という技術者の発案で開発した製品です。
開発に取り掛かったのは間違いなく当社が一番手だったのですが、製品としてのリリースはほんの少しの期間だけ他社に先を越されてしまいました。

- 佐々木
- ラジコン草刈機に対し、お客さまはどう評価されているのですか。
- 重見
- 実はラジコン草刈機は、コストありきではなく、こういうものが作りたい、という理想形を重視して開発した製品です。そのため、性能には自信がありましたが、価格が競合製品の1.5倍ほどになってしまい、当初は私たちも「本当に売れるのだろうか」と不安を感じていました。そんな中、完成後お客さまの前で動かしてみせた際に「おおー」と歓声があがりました。他社製で試行した時は、急斜面すぎて機械が動かなくなったところをきれいに刈ることができたのです。あの歓声を聞いた時に、「これは売れる!」と確信しました。おかげで発売以来、順調に実績を重ねてきました。現在はラジコン・乗用・歩行型の草刈機シリーズで、売上の半分を占めるほどになっています。
他にはない機能を実現するのが技術者の任務。
- 佐々木
- 様々なオリジナル製品を開発しておられますが、開発テーマはどのようにして生まれるのですか。
- 重見
- 研究開発部の技術者が独自に持ってくる場合もありますし、お客さまの声を聞いた営業サイドから上がってくることもあります。
私たちは、最先端の技術を詰め込んでいるわけではありません。しかし開発にあたっては、常に今までになかった新しい発想やアイデアを形にするようにしています。当社の創業者、村田栄一は「科学者は新知識の追求が任務であり、技術者はその知識を応用して新しい方法や開発を進めるのが任務である」と言っています。他の製品にない特徴を必ず実現する。これは当社に根付いたDNAとなっているのです。 - 佐々木
- 技術者が製品の使用現場を見に行くことはあるのですか?
- 重見
- 結構行きますね。現地での製品テストも、当社は技術者自らの手で行いますから。開発者が設計したものを自分でテストし、評価まで行う会社はあまりないのではないでしょうか。
そんな大変なことをなぜわざわざやるのかと言うと、得られるものが大きいからです。現場で実際に使ってみて、これで作業が楽になる、と実感できた製品は、ヒットすることが多いです。やはりユーザー目線が大事なのです。現地で試して気付きがあれば改良するなど、新たなアイデアも盛り込めるので、テストを繰り返すうちに良くなっていくんです。
私も乗用草刈機を開発していた頃、青森に行って1週間位かけてテストをしました。すると、草を刈る機構のカバーの上に刈った草がどんどん乗っていくのを見て「これは乗らない方がいいのではないか」と感じました。そこで、回転する装置の下に羽をつけ、風を起こして草を飛ばすように改良したのです。おかげで使い勝手が向上し、お客さまの評判もよくなりました。現場でテストしなければ、そういった問題に気付けないということもよくあります。 - 佐々木
- 次に狙っているのはどんなテーマでしょう。

- 重見
- 今後、農業人口は減少しますし、高齢化も進んでいます。個人で農業をやるのは難しい時代になるでしょう。手広く効率的にやっていかないと、事業として継続できない。となると、必要になるのは自動化です。
自動化した草刈機は海外には既にありますが、国内はまだです。掃除ロボットのような小型の製品は見かけますが、草刈り範囲を設定すると自動で草を刈る本格的な草刈機が出てくるのはこれからです。近くで人間が見守るタイプだと比較的容易ですが、それでは自動化機械として不十分ですよね。本命は、人間がその場にいなくても機能する遠隔監視型だと思います。ただしそうなると、センサーもカメラも新たに必要で、技術的なハードルが一層上がります。それを実現するには、電気に詳しいエンジニアが必要です。
電動車いすもバージョンアップしていきます。高齢者ご本人はもちろん、ご家族も安心できる機能を付加したいですね。高齢者を一人で外出しても安心なように、見守りの仕組みを備えるとか。また、衝突・転落防止の技術など安全性を向上させるため、大学と共同研究も行っています。 - 佐々木
- 農業・福祉以外の分野への展開についてはいかがですか。
- 重見
- ラジコン草刈機を開発して以降、農機具としてだけでなく、建機としても扱ってもらえるケースが増えました。そこで、建機分野でも使える乗用草刈機にも取り組みたいと思います。建機となると、草を刈る面積が格段に大きいですし、稼働時間も長くなります。冬以外のほとんどの時期で動かすことを考えると、高い耐久性が要求されるでしょう。
海外市場開拓にも力を入れていきます。海外ではまたニーズが異なるので、日本と全く同じものを持っていっても売れません。実は2016年に、フランスのシャンパーニュ地方へ行き、ブドウ畑を調査したことがあります。現地ではブドウの木と木の間隔が日本の果樹園より狭く、傾斜もあって大きな機械が入れません。そこで、現地の状況に合わせた、フランスのブドウ園専用の草刈機を翌年に開発しました。
当社にはこれまでも、農家や現地の状況に合わせて細かくカスタマイズを繰り返してきました。この経験は、海外展開を進める上でも強みになってくれそうです。
変革を受け入れる柔軟な風土。
- 佐々木
- 西本さんは経営企画部で人事をご担当されていますが、どういう経緯でアテックスに転職することになったのですか?
- 西本
- 大学を卒業後、農機具関連の販売会社に就職し、人事総務に配属されました。3年後、人材採用支援の会社に転職して大学生の就職サポートなどを担当。2年後に再度、コンサルタント会社に転職し、人事評価制度の策定などを行いました。しかし人事評価は企業経営の上で根幹となる制度なので、性急に案件を処理するのではなく、個社ごとの状況を踏まえて大切にやっていきたい、という気持ちが起こったのです。そこで3度目の転職を決意。転職活動の末、アテックスに入社することになりました。

- 佐々木
- 入社当時と比べ、アテックス社の印象は何か変わりましたか。
- 西本
- これまで所属した会社は全国展開をしている大手の企業が多く、地域に根差した会社に就職するのは初めての経験でした。大きな価値観のギャップがあるのではと少し心配をしていましたが、実際に仕事をするうち、大手ではできないことがここではできる、と実感するようになりました。
大きな違いを感じたのは意思決定の早さです。「こういう制度を取り入れよう」「こういうことを実践しよう」と提案すると、大手では決済までに非常に時間がかかることが多かったのですが、ここではスピード感をもって意思決定されることが多いのです。
私は今、経営企画部に所属していますが、この部署の設立も私たちの声から始まっています。100周年を迎えるにあたり、他社の取組みなどを拝見する中で、何か新たなチャレンジをしていく必要性を感じました。その先駆けとして、「これからの経営や事業の戦略を描く組織を持った方がいいのではないか」と役員会で提案してみたのです。正直なところ、すんなり通るとは思っていませんでしたが、その経営会議の場で「確かにそうだ」と賛同が起き、部門が立ち上がることが決まりました。そのようなスピード感です。 - 佐々木
- そういう提案を受け入れる風土があったのですね。
- 西本
- 入社前は、100年近くの歴史がある会社なので、ともすると過去に固執する傾向があったりもするのかな…とも思っていましたが、全く違っていました。今日、重見のお話を横で聞く中で、その理由もわかった気がします。現場を見たり、お客さまの声を採り入れたりすることでオリジナルの製品づくりを行う、という積み重ねによって、時代の変化を取り入れる柔軟性が培われたのでしょう。
私の入社したタイミングが、ちょうどラジコン草刈機がヒットした頃でした。これにより業績も良くなってきたし、いろいろいい方向に進んでいると思います。ベースアップも実施し、賞与も上がりました。休日を増やしたり、副業を認めるなど、時代の変化に合わせて会社も変わってきていると感じています。
現場を見て、お客さまの声を聞く。それが理想の設計につながる。
- 佐々木
- 西本さんの提案もあって経営企画部が設立されたわけですが、アテックスの100周年に向け、何を目指されますか。
- 西本
- 総体的に思うのは、人事として、従業員の納得いく環境を作りたいということです。アテックスが、高いポテンシャルを持っているのは確かです。重見のような技術者と話をすると、実はすごい製品づくりしているのだとわかります。当社の技術開発部が「世の中にあるものを作っても意味がない。ない物を作る。」というスローガンを掲げていることは知っていましたが、過去にこれほど多くの「初めて世に出す」製品を生み出していたことに驚いたと共に、社員でさえもちゃんと理解できていないのではないかと感じました。

- 重見
- 私が30歳前くらいの頃、メインとして開発を担当したのが堆肥散布車「マキタロウ」です。マキタロウには「堆肥を自動で積み込む」という機構を採り入れたのですが、これも当社が初めて搭載したものです。実現にはだいぶ苦労しましたが。
- 西本
- あまり知られていないのですが、実は石材運搬車についても当社はシェアトップなのです。そういう事実は、技術系でない他の社員ともっと共有した方がいいですよね。もちろん社外にも積極的に発信していくべきです。アテックスの開発志向や具体的な取り組みを知ってもらえば、世の中に役に立つものを自らの手で開発していきたいという技術者が興味を持ってくれるかもしれません。
また、人事評価もレベルアップを図りたいと思っています。自分のどこが評価されているのか、その結果が何に反映されているのか、評価される側がきちんとわかる仕立てにしたいですね。この点では、私の前職経験が活きると思います。 - 佐々木
- どんな人材がアテックスにマッチすると思われますか。
- 重見
- ものづくりが好きなのは大前提として、現場に行って、何に困っているのかを見て、それらを解決できる機構を組み込んでいく、というやり方に意欲を見出す人が向いていますね。出荷後のフォローや調整もやるし、不都合があればどんどん改良していく。そういったきめ細かな対応が、お客さまの信頼を生むのです。お客さまから要望が上がっても要望に細かく答えることはできない会社もある、と聞きますが、そういう姿勢に疑問を持つエンジニアは、当社では活躍の幅が広がります。また、理想の設計を追求したいと考えるエンジニアも、当社にマッチすると思います。当社には「初めて世に出す」製品がたくさんあります。こういう製品はあまりコストに縛られず、満足の行くものづくりができます。
- 西本
- 自分で設計したものが形になる瞬間に喜びを感じる。そういう人がアテックスには合うでしょうね。
- 佐々木
- 最後にお二人にお聞きしたいのですが、四国の地で働く価値観、魅力はどういうところにあるとお考えですか。
- 重見
- 出張で東京などに行って、松山に帰ってくると、ホッとした気分になりますね。ずっと人混みの中にいると、窮屈ですよ。愛媛は気候もいいし、災害も少なく、住みやすい街です。
仕事については、日本全国、時には海外ともビジネスを行うので、地方にいるから遅れている、という感じもありません。

- 西本
- 結婚して子育てしている立場から言うと、両親が近くにいる地元で暮らすのは心強いです。子どもが急に体調を崩した時などは手を貸してもらえるし、子どもを連れて遊びに行くと両親も喜びます。仕事の暮らしのバランスは、ローカルの方が良くなると思います。
大都市圏の大手企業と比べると、地方の会社の規模が小さくなるのは否めません。ただ、組織が小さい分、自分が主導できれば大きな影響を与えることができるというやりがいもあります。技術者で言えば、一つの開発を任されるわけですから、当然やりがいも大きいでしょう。私たち人事畑の人間でも、人事の制度づくりや組織づくりから携われるので、面白く仕事ができると思います。 - 佐々木
- 技術面・人事面に通じたお二人がやりがいを持って働いておられることがわかり、改めてアテックスという会社のポテンシャルの高さを実感できました。
本日はどうもありがとうございました。

重見 和男
(株)アテックス 取締役・研究開発部長
愛媛県出身。愛媛の大学で機械工学を学ぶ。就活ではメーカー中心に企業を探した。実家が農業を行っており、アテックス製の運搬車を農作業で使っていたことから同社に興味を持ち、就職を決意。1988年に(株)アテックスに入社。以後、一貫して研究開発部の技術者として製品開発を担当。作業用運搬車、堆肥散布車、歩行用・乗用・ラジコン草刈機、電動車いすなど、同社で発売される全製品の開発に携わる。現在も、研究開発部の部長として新製品の研究開発を担っている。

西本 大介
(株)アテックス 経営企画部(人事)主査
愛媛県の大学を卒業後、2013年に大手農機具メーカーに就職。人事総務の仕事を担当する。3年後、大手人材サービス会社に転職し、大学生の就職支援を担当する。その後、コンサルティング会社に転職し、人事評価に関するコンサルタントを行う。2019年、(株)アテックスに転職。経営企画部で人事を担当する。

佐々木 一弥
(株)リージェント 代表取締役社長
香川県さぬき市出身。大学卒業後、2007年に株式会社リクルートに入社。求人広告の企画営業職として、香川・愛媛にて、四国に根差した企業の採用活動の支援を中心に、新拠点や新サービスの立ち上げも経験。2010年に販促リサーチを行うベンチャー企業の創業メンバーとして参画。創業の苦労と挫折を経験。2012年、株式会社リージェントの創業メンバーとして入社。2019年より代表取締役社長に就任。子どもと焚き火をするのが至福の時間とのこと。